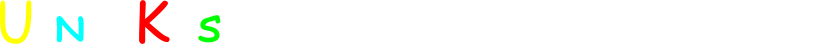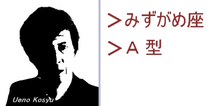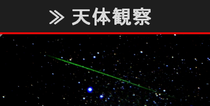月山2001
山と自然 一歩一歩登った山々に美の原点がある!
月 山 芭蕉が「奥の細道」で登った山 標高 1978m
2001年8月16日(木) spectator:2129
- 清見川と老ヶ岳分岐の途中から
東北の山旅を思い立ったのが、2001年の夏のことである。
候補はいくつかあったが、出羽三山の「月山」にしぼった。
松尾芭蕉が「奥の細道」で唯一登山した山、あの名句の印象が強く残っていた。
「雲の峰 いくつ崩れて 月の山」
コースは、湯殿山からの往復とした。
芭蕉が頂上から往復したコースを逆に辿ることになる。
8月16日早朝、新潟を出発。7号線を北上し、湯殿山の有料道路に入り、駐車場に車を停める。
そこから本宮までバスで数分の道。バスは参拝者で満員。登山者は我々夫婦二人だけだった。
バス停から本宮のご神体までは、幟が並んだ道を少し下る。
ご神体は板などで隠してあるが、お湯の湧き出る大きな岩だということは公然の秘密となっている。
見学しようと思ったが、案内するマイクの声が神聖な場所に似つかわしくない大音響で騒々しく興ざめだ。
商業主義然としているようで不快に感じ、きびすを返して登山道に向かう。
登山道入り口の標識がご神体のすぐ先にあり、その右前方の御幣が渡された禊の川を過ぎると、三つの月光坂と名付けられた急登がはじまる。
最初の急坂が「水月光」みずがっこう、と読む。
登山道はよく整備されていて道に沿って流れる小川にはオタカラコウ、トリガブト、目の覚めるような青色のガクアジサイなど次々に迎えてくれて心を和ませる。
ゆっくり撮影しながら高度を上げてゆく。
うっそうとした木々の下に壁のように立ちはだかる岩場の「金月光」が現れ、長い鉄梯子や鎖が数か所架かる。
そこを登りきると見晴らしのいい「装束場」に着く。
ここには装束を改めるための小屋が建つ。いざというときの避難小屋にもなる。
はるか下に茶色の露岩の本宮ご神体が見える。
ご神体は薬師岳の麓にあり、薬師岳(1262m) の左に標高1500mの「湯殿山」が連なっている。湯殿山には登山道はなく、登れない山となっている。
出羽三山とは、月山、湯殿山、そして羽黒山であるが登れる山は月山だけである。
装束場からの登山道はゆるやかな草原がひろがり、ニッコウキスゲやキンコウカ、イワイチョウなどが群落していてホッと一息つけるエリア。
風と光を感じながら気分よく歩く。
清見川のせせらぎを渡って草原を右に見てひと登りすると姥が岳の分岐に出る。
ここが金姥だ。頂上と反対側に姥ケ岳(1670m) の頂上が指呼の先に見える。
姥ケ岳方向からはロープウエイで登ってくることができる。
眼下には広く平淡な草原が広がり、その木道には大勢の登山者が列をなしている。
山頂はガスがかかっていて見え隠れしていてどことなく神秘的だ。
そこからの石畳のように整備された広い登山道には様々な種類の高山植物が顔を出す。
右方向に、ガスが晴れて雪渓が現れた。
ここは夏スキーで有名な場所で、気持よさそうにジャンプしながら滑走するスキーヤーがガスのなかを下ってゆくシーンはとても幻想的である。
草原のルートとの分岐点の牛首からは、いよいよ最後の急登「鍛冶月光」にとりつく。
かなりきつい登りを喘ぎながら行くと、ようやく今日泊まる「鍛冶小屋」に着いた。
ここはお風呂があって、夕日に暮れなずむ山々を見下ろしながらの入浴はこの上ない贅沢を存分に味わうことが出来る山小屋だ。しかも一人だけの貸切り風呂である。
まさしく、いくつもの雲の峰に残照となって光と影を落としてゆく様は、芭蕉の俳句と重なって神々しく見えた。
山頂での風呂上がりの夕食に飲んだビール。
感想を述べるまでもないだろう。
今宵の宿泊客は我々夫婦とちょっと変わった感じの若い女性の3名だけだった。
その夜は、ちょうどペルセウス流星群がピークの日。
布団を窓際に敷き、眠りにつくまで満天の星空に白く長い光跡を引くたくさんの流星を楽しむことができた。
こんな贅沢な夜空の展望台はない。
鍛冶小屋の少し上に芭蕉の句碑が建っている。その先は広い草原になっていて、左側のちょこんと小高く突き出た三角形の山塊全体が神社になっている。
山頂に立つという達成感が得られないのは信仰の山であり、致し方ないのかもしれないが神社に立ち入るのに有料とは世知辛いものだ。
月山は出羽山地では鳥海山に次ぐ標高をもち、月読命を祭神とする「月の山」である。
芭蕉は曽良と旧暦 1689(元禄2)年6月8日、別当代会覚阿闍梨らの勧めで、宝冠をかぶり、木綿しめをかけた装束で月山に登った。
奥の細道に
「… 強力といふものに導かれて、雲霧山気の中に氷雪を踏みて登ること八里、さらに日月行道の雲関に入るのかと怪しまれ、息絶え身凍えて、頂上に至れば、日没して月顕はる。
笹を敷き、篠を枕として、臥して明くるを待つ。日出でて雲消ゆれば、湯殿に下る。
谷のかたはらに鍛冶小屋といふあり。この国の鍛冶、雲水を撰びて、ここに潔斎して剣を打ち、つひに月山と銘を切って世に賞せらる。
かの龍泉に剣を淬ぐとかや、干将・莫耶の昔を暮ふ。道に堪能の執浅からぬこと知られたり。…」と、ある。
芭蕉は、翌日6月9日に頂上から今回の登山コースを往復し湯殿山を参拝して月山山頂にとって返し、入山口の南谷まで下り帰った。
旧暦の6月はまだ積雪の登山道、当時のいで立ちを考えれば強靭な体力の持ち主で、すこぶる健脚である。
「総じてこの山中の微細、行者の法式として他言することを禁ず。よって筆をとどめてしるざす。坊に帰れば、阿闍梨の求めによりて、三山巡礼の句々、短冊に書く」
あの名句はそこで詠んだものだ。
芭蕉は生涯で一番高い山に登ったのがこの月山であった。
江戸時代の芭蕉の登山を思いながら、朝食前の朝の頂上散歩に出る。
8月17日、早朝のガスも消えた快晴の中、気持ちのいい草原をしばし堪能しながら朝日に輝く花々を撮影した。
山頂直下の平淡な草原では、ハクサンシャジン、ハクサンフーロ、ハクサンイチゲ、コバイケイソウ、ミヤマキンポウゲなど見事な花の楽園をつくっている。
下の池塘にはめずらしい太陽柱のような現象も見ることが出来た。
遥かに連なる東北の青い峰々は夏空に映えてどこまでも続き、足元にはお花畑。月山は名実ともに東北の名峰であり、花の名山である。
- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)
a:2129 t:1 y:0