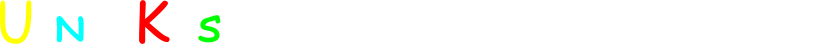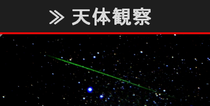いけばなの美学-1
■ いけばなの美学-1 (いけばなの多様な発展を促したもの。)
2010年2月3日(水)
日本人の美意識と価値観
21世紀の今日では非常に多様な価値観が存在する。そんな中で人間の美意識に対する価値観はどのように変化してきたのだろうか。
人間が何かを見てその対象を美しいと感じるとき、同時にそれを見る自分自身の感性の琴線が共鳴し、その瞬間は一切の拘束から解放されて自由な心を呼び起しているときである。
人が「美」に対して飽くなき願望を求めるのはこのためでもある。
この美しいという観念は心の内からつくりだされるものであって、決して外から与えられるものではない。
その美の対象の中の造形の個性と己の感受性が共鳴して美しいという観念が生じるのであり、豊かな感受性を育むには己の感性を磨くことが重要になってくるのだろう。
美の感動には、時代を超越した造形様式と時代と共に変る造形美というものがある。
そこには、いかなる芸術分野においても伝統的なものを越えていく、否応なしに常に新しい美を創り出してゆく人間の宿命のようなものが存在する。
その新しい美の意識が時代に反映され、時代の琴線と共鳴して我々に感動を与えるのである。
しかし、それは移ろいやすい不安定さを常に持ち続ける存在でもある。
初めて見て感動を覚えた絵画にしても音楽にしても映像にしても、最初の感動が同じレベルで持続するとは限らない。
人間は意識の慢性化がおこるものだし、次から次へ新しい関心に移る存在でもあるからだ。
時代時代のなかで創られる美の価値観というのはその時代と共に絶えず変化していく存在ともいえる。
そんな移ろい行く時代の変遷のなかで、唯一変らないものがある。それはこの地球の大自然である。
美しい花を見て感動する心は人類普遍の感情である。花を見て怒り出す人はいないであろう。
四季に咲く花や草木は、意識の慢性化を起こさない適宜な周期で形を変えながら現れては消えて一年というなかで巡り来る。
そこにおける自然の美しさはこの循環する宇宙の輪廻の中に普遍的に存在し、四季のなかで毎年繰り返す。
もし、日本が砂漠のように一年中変化しないような四季のない自然だったとしたら、いけばなも他の芸術も今日のような日本的な美意識の存在を喚起することはなかったであろう。
すべての美の原点として学ぶべきところが、この美しい地球の大自然のなかにある。
時代を超越した素晴らしい芸術作品は確かに存在する。
その美の本質的な根源も唯一普遍的なこの大自然の世界観の中から生れてきたものと考えてみたとき、本物の持つ美しさ、本物の芸術は時代を超越した価値観を持つのではないだろうか。
日本人と花とのかかわり
花は季節に先駆けて咲く。常盤木は冬でも青々とした生命を保つ。古来人間にとって植物は神の宿る「依代」として神聖視されていた。
植物の持つ生命力にあやかろうとして身につけたり、観賞したことは古くから記録に残る。
万葉集には、三分の一の千五百首に約160種の植物が登場し、最も多く詠まれた萩には、手折ったとたん、みるみる枯れていくのでオロオロするといった情景が詠われている。
仏教伝来の六世紀以後の供花として仏前に供えられていたことが絵巻などで知ることができるが、平安時代初期、大同二年(807年)九月に、嵯峨天皇(当時の賀美野親王)が兄の平城(へいぜい)天皇に神泉苑行幸の折、
「宮人(みやびと)のその香に愛(め)づるフジバカマ 君のおおもの(御物)手折りたる今日」
と詠み、菊(フジバカマは菊の異名)をいけて献上したことが「類聚国史」に記録されている。
さらに延喜五年(905年)「古今集」のなかで初めて「花を挿す」という言葉があらわれる。
また、「万花会(まんかえ)」という豪華な供花や、庭に花を寄植にして縁側から観賞した「前栽合せ」や、遊びの要素が加わった「花合せ」のように、平安時代の貴族社会では花の豪華さを競ったりする遊びが「歌会」とともに行われていた。
しかし平安時代では花の観賞の場の主流は主に家の外であり、庭に植えた季節の花を愛でる様子が多くの大和絵に見ることができる。
例外的に枕草子で高欄にて桜を投げ入れて観賞する記述が見えるが、これは和歌を詠むために近くで観賞するためだったことによるものだろう。
平安時代の寝殿造りでは室内で花を飾るという記述はほとんど見当たらない。
鎌倉時代の後期ころになると中国から大量の唐物(からもの)と称する美術工芸品が輸入され、花を挿して観賞するという記録がでてくるが、未だそれに法式を持たせるというところまではいかなかった。
花の法式の成立
十五世紀、室町時代になると日本人の美意識が、「幽玄」や「わび、さび」といった感覚的な美の域を超えて精神的な風韻(ふういん)を尊重する特色を持つ。
これは中国から輸入された仏教思想(特に禅宗の影響が大きい)、老荘思想または儒教思想が大きな影響を与え、そこから日本独特の日本的思想となり、日本人のモノの見方、考え方に大きく影響を与えることになる。
部屋の中に唐物などを飾り付けをするための専用の場所が作られると、やがて本格的な「床の間」が出現する。
足利義満、義政の近習に特殊な芸能集団「阿弥衆」がいて、能、作庭、いけばな上手などを輩出し、室内のしつらえの基礎を作った。
このころから盛大ないけばな展が行われている。
最初は珍しい舶来の器(唐物)の品評会から、用途に合わせて花を生けていったのが華やかないけばな展のようになったものだ。
そして、新しいインテリアになった床の間が住居の中心に据えられ、ここにしつらいの花としていけばなが飾られるようになった。
これが室町時代の「書院造り」という建築様式のなかで定着する。
儀礼的な接客が重視された時代にあって御殿(ごてん)建築様式のような大建築が登場する。
豪華なものは将軍御成(おなり)や祝言など接客をたてまえとする座敷中心に構成され、床の間に違い棚,付書院,それに帳台構えが備わり、技巧を凝らした欄間や格(ごう)天井、壁面や襖には金碧の障壁画が描かれた。
そこに室内装飾として格調高く花を立てることが求められ、いけばなは次第に大型化する様式となって広まってゆく。
初期の立花(たてはな)
立花は、単に花を立てるのではなく、自然の素材から抽象化された形として整えることで、はじめて芸術となりうる「型」として工夫されてゆき、正式の床飾りとして真の「荘厳(しょうごん)の花」として洗練されてゆくことになる。
最古のいけばな伝書として1445年に相伝されたとする「仙伝抄」がある。
この時期に著された伝書をまとめたものである。したがって著者も年代も不明となっている。
書院造の座敷飾のマニュアルとしての伝書が阿弥衆によって著される。
能阿弥が著した「君台観左右帳記(くんだいかんそうちょうき)」(1471年)である。
また、同じ時期に同じような生け花の伝書が著されている。それらはほとんど写本で相伝されて現存するため作成年代は不詳となっているが、お手本があってそれに著者の考えを増項していったのではないかと推測される。
それらの中で「たて花」が最初に法式をもつ様式として成立するのだが、同時に自由に「入れる花」も後の「茶花」や「なげ入れ」の原型として考えられていた。
このバランス感覚がいかにも日本的と思えるのだが、この規律を重んじる様式と、自由にいける様式が時代の推移の中で交互にその時代の様式の主役になって登場してゆくのである。
初期の立て花の考え方は、真直ぐ立てた真を仏、枝を神、下草を人とするように仏教思想が反映され、開く枝は慈悲、抱く枝は智慧というように、「右長左短」を型として三具足の花から発展した仏教的理念を色濃く摂り入れてその規矩を定めていた。
立花(たてはな)の構成の基本は「円相」で、禅宗における人間の出生の平等観から形成されている。
また、縁起を重く見ている風潮もこの時代の特徴であり、生と死に関連する禁忌の決まりごとが多く、武家社会を中心とする生活に密着した考え方が取り入れられていた。
その最初の様式には、美の原理というより造形そのものに縁起の良し悪しが優先されていて、当時の時代背景がそのまま造形にも反映されていたのである。
室町時代に起こった応仁(おうにん)の乱(1467年~77年)は、京都中が灰燼(かいじん)に帰したといわれるほど壊滅的被害を与え、十年もの長きにわたる動乱期が続いた。
貴族社会ではすでに座敷飾が定まっていたが、この戦乱で多くの装飾すべき唐物(からもの)などが喪失した。
その装飾品の空いた空間を補う役割を果たしたのが、いけばなであり、それが当時の代表的様式の「立花(たてはな)」であった。
そこで御所や大寺院などの書院造りの大空間にふさわしい大振りな作風とするため、花器も、唐物にかわり身近にある馬盥(たらい)などの大きな器が代用して使われた。
この大きな空間に飾る花の装飾方法が考え出されることで、宗教的に定型化していた床飾りから一歩進んだ手法が創意工夫され、芸術的な造形として生み出されてゆくことになる。
その空間環境に応じて創りだす手法は「おのずから興ある風体を創りだす」こととなり、ここに法式としての立花(たてはな)の造形論を明確に述べた「池坊専應口伝」(1523年)が著された。
これがはじめていけばなの理念と本質について述べられた花伝書である。
「いけられた花そのものの美しさ」がいけばなの対象になるのではなく「いけられた作品そのものの美しさ」がいけばなの対象になるとした。
と、まず一般的な挿花と芸術的挿花の違いを明確にしている。
その序文に、立花以前の花は、何ら技巧のない単なる自然のままを有り様に入れただけだったと断じ、続いて「この一流は、野山水辺をおのずからなる姿を居上あらわし…」花の造形は、自然の再構成を目指すとして、「…ただ小水尺樹をもって江山数程(こうざんすうてい)の勝がいをあらわし、暫時頃刻(ざんじこうこく)の間に千変万化の佳興をもよおす。…」と、少ない水と短い花木で大自然の景色を創る。
そこに見えないものも見えるようにするという抽象化、虚構による造形論がうたわれた。
「虚と実」による造形論である。
「暫時頃刻の間に千変万化にもよおす佳興」とは花の持つ有時間性をいい、自然の摂理をも見定めている。
この「自然のおのずからなる姿」「小水尺樹による自然の抽象的表現」「自然のもつ命」への自覚が、後出する多くの花伝書、それは立花だけではなく今日まで続くいけばな全体の理念の底流となって花の造形論の規範となるものであった。
ここにはじめていけばなが理論を持った様式美として出現したのである。
以後、様々ないけばな様式が時代と共に成立してゆくが、江戸時代末期まで、この「池坊専應口伝」の理念がその基本にあると言って過言ではない。
その立花(たてはな)は江戸時代初期(十七世紀)に、二代目池坊専好(せんこう)の時代に大成する。
そして専好と第109代後水尾天皇との出会いがいけばなの発展を確固たるものにしてゆくのである。
(いけばなの造形美-1 終 )
- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)
a:10180 t:4 y:1