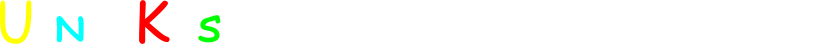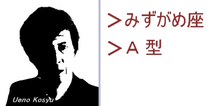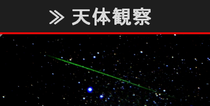古事記の動植物
■ 古事記に登場する動植物‐1 (古事記完成千三百年の年によせて)
2012年4月13日(金)
古事記と日本書記と万葉集は、7世紀半ばすぎから8世紀はじめにかけてほぼ同時期に日本で初めて著された現存する最古の文献である。
最も古くに完成した古事記は、それまでの伝承されてきた歴史をまとめた壮大な叙事詩的な物語で、今年でちょうど編纂千三百年目の節目となる。
そこで、古事記のなかに出てくる動物や植物を抜き出してみた。
上巻二十二項のうち、十四項のなかにいろいろな動植物が登場する。
そこから、古代の人々の生活感覚と動植物とのかかわりが見えてくる。
古事記 上巻(かみつまき)
上巻ではこの国の成り立ちから初代天皇神武天皇の出現までを神話の世界のなかの物語として展開する。
1、宇宙のはじめ。
神代の時代にまだ宇宙が混沌とした時代。「あたかも海月(くらげ)が水中に浮かんでいるような頼りないところへ、水辺の葦が一斉に芽吹いてくるようにして神が現れた。」
開墾も埋め立ても十分に行われていなかった当時、ぬかるみの多い湿地帯がシベリアの荒野のごとく広がっていて、浮島のようなところには葦が生えているという風景が目に浮かぶ。
3、伊邪那岐命と伊邪那美命
イザナギとイザナミがこの世ではじめて子である神を生もうとするのだがうまくいかない。そこで天の神(天神(あまつかみ)に尋ねると、牡鹿の肩骨を焼いて割れ目の形で吉凶をはかるという太占(ふとまに)の占いをたてた。
ここから、古代から占いは動物の骨が使われていたことがわかる。
二人は日本列島の島々を生み、次に建物にかかわる神々を生み出してゆき、さらに生活の場となる海や川の水にかかわる神を生んだ。
それから、風の神を生んだ後、木の神、山の神、野の神を生み、そして山と野をつかさどる神を生んでゆく。
さらに続けて、水鳥のように速く進む楠で造った船をたたえた交通の神を生んだ。
火の神を生んだことでイザナミが病に倒れ、そのときに鉱山や肥料や水や穀物など食物をつかさどる神々が生まれた。
イザナギは亡くなったイザナミに会いに死者の国「黄泉国(よもつくに)、根の国、根堅洲国(ねのかたすくに)とも書く」に行くが、妻のおどろおどろしい腐れ果てた姿を見てしまい、恐怖に駆られて一目散に逃げ出すのだが、怒ったイザナミは黄泉の国の醜い女神たちに命じ後を追いかける。
イザナギは近づかれそうになると、頭に着けていた黒い蔓をとって投げ捨てる。するとそこから野葡萄の実がなり、それを女神たちが食べている間に遠くに逃げる。
再び追いつかれそうになると、今度は髪に挿してあった櫛の歯を折って投げつけた。
するとそこから竹の子が生え、それをまた女神たちが食べあさっている間に遠くに逃げた。
次にイザナミの体から生まれた雷神たちに千五百人もの軍隊をつけて追いかけさせた。
イザナギがようやくこの世の境の坂までたどり着くと、追いかけてきた軍隊にそこに生えていた桃の実を三つ投げつけて退散させたのだった。
似たような話は、西洋にも中国の桃源郷の故事にもある。
7、天の岩屋戸
日の神、アマテラスがスサノヲの悪行を恐れ天の岩屋にこもり、その岩戸をぴったり閉めてしまったため、世の中が暗黒に包まれた。
何日たっても太陽が現れなかったので、八百万の神々が集まって相談した。
そこで知恵者のオモヒカネノカミの謀が採用された。
まず、長鳴鳥の鶏を多く集め、一斉に鳴かせる。そして、つぎに鏡や長い玉飾りを作らせ、天の香具山に生える朱桜(ははか)の木の皮で牡鹿の骨を焼く鹿卜(しかうら)の占いをさせてその謀を神意に尋ねた。
その結果よしとなったので、天の香具山に生える青く繁った榊の木に玉飾りや鏡を懸け、下枝には白い木綿の和幣(にぎて)や青い麻の和幣を飾った。
この和幣を両手に捧げて祝詞を奏上した。
男勝りの女神のアメノウズミノミコトが天香山にはえる日蔭蔓をたすきに懸け、頭には正木葛(まさきかずら)を巻き、さやさやと鳴る笹の葉の束を手に取り、天岩戸の前で足拍子面白く、音も轟くばかりに踊った。
この様子に高天原が揺れ動くと思われるほどに集まった八百万の神々が声を合わせて笑った。
こうして、アマテラスの好奇心を引き出し岩屋戸から引き出すことに成功する。
8、須佐之男命の追放・穀種
スサノヲの乱暴狼藉から端を発したこの事件でスサノヲは神々から処罰され高天原から追放されることになった。
地上へ追放される前にスサノヲは食物をつかさどるオホゲツヒメノカミに食べ物を所望したが、姫は己の鼻や口や尻から不浄のものを取り出して作り上げた食べ物をスサノヲに差し出した。
これを盗み見していたスサノヲはたちまち荒い気性が起こりこの姫を殺してしまうのだった。
すると、この姫の体から様々なものが生まれた。
頭には蚕が生まれ、目からは稲の種が生まれ、耳からは粟、鼻からは小豆、下腹からは麦、尻からは大豆が生まれた。
そこで穀物の祖先の神となったカミムスビミオヤノミコトがこれらの五種の穀物を種とした。
11、大国主命とウサギ
オオクニヌシノミコトには八十人の兄弟がいたが、いつも兄達に虐げられていた。
ある日、出雲国から因幡に打ちそろって出かけたが、オオクニヌシには大きな袋をかつがせて、いつも従者のように扱うのだった。
オオクニヌシオミコトが一番最後から歩いてゆくと、皮膚を剥がれた兎が泣き喚いている。
訳を尋ねると向島に渡るのにワニを騙して渡ろうとしたが嘘がばれて皮を剥がされてしまった。
そこへ通りかかったオオクニヌシの兄弟の神々が海に入って空風の吹くところで乾かすようにいわれたのでそうしたら乾いてゆくにつれ皮が引き裂かれあまりの痛さに泣き転がっていたのだという。
そこでオオクニヌシノミコトは真水でよく身体を洗い清め、蒲の花の黄色い花粉を敷き、そのうえを転がって肌に擦り付けるようにと教えた。
兎は教えられたとおりにやってみるとやがて元通りのきれいな体に戻ったのだった。
これが稲葉の素兎(しろうさぎ)の話である。
12、大国主神の受難
稲葉に着くと、兄弟たちはヤカミ姫に結婚を申し込むのだが、姫はオホナムヂノ神(大国主命)と結婚すると答えた。
怒った兄弟たちは大国主命を殺す計画を立てる。
そこで、「この山には赤い猪がいる。我々が上から追い出すので、下で捕まえろ。失敗すればお前を殺す。」といった。しかし、猪の代わりに大きな石を真っ赤に焼いて、これを突き落とした。
この石を猪と思ったオホナムヂノ神はそれを抱きとめた瞬間黒焦げになって死んでしまう。
この知らせを聞いた母神は天の高天原に行って生成をつかさどるカミムスビノ神に助けを求めた。
神は、赤貝のキサガキヒメと、蛤のウムギヒメを遣わして死んだオホナムヂノ神を治療し生き返らせた。
このあと、もう一度兄弟たちの殺されるのだが、またもや母神の力で生き返える。
すると、また兄弟たちは執拗に殺そうと追いかけてくるのだった。
13、根の国での冒険
この度重なる危難を見た母神は、オホナムヂノ神(大国主命)に祖父であるスサノヲ命(大神)の住む根堅洲国(黄泉の国)へ旅に行ってくるよう命じた。
オホナムヂノ神はスサノヲの住む宮殿に着くと大神の娘のスセリ姫と会うなり一目ぼれし、二人は夫婦になった。
大神はオホナムヂノ神を見て葦原色許男(アシヨシハラシコヲ)と呼んで宮殿に入れたが、好ましく思わなかった大神は蛇の住む室のなかに泊めるのだった。
このままでは命が危ないと思った姫は蛇を払いのける魔法のヒレを渡す。次の日はムカデと蜂の住む室に泊められたが、そのときも姫のおかげで無事にあくる朝室から出ることができた。
つぎに、大神は鏑矢を果てしない野原に打ち込んで拾ってくるよう命じておいて野原一面に火を放った。
逃げ場のなくなったオホナムヂノ神を救ったのが鼠だった。身を隠す洞窟のありかを教えて、さらにその鼠が鏑矢を口にくわえて来てオホナムヂノ神に差し出した。
軽い羽のほうはその鼠の子供たちが総がかりで運んできてくれたので無事に命じられた矢を差し出すことができた。
今度は大神の頭の虱を取るよう命じたが、それは百足の巣のようなものだった。
そこでスサリ姫は、椋の木の実と赤土を夫に渡してそれを口に含んで吐き出させたので大神はてっきり百足を噛んで吐き捨てていると思い、ついに眠ってしまった。
そこからスサリ姫との大脱走になるのだが、その先の話はここでは省く。
14、沼河姫の歌
大国主命は、越の高志の国(新潟県糸魚川)の沼河比売(ヌナカハヒメ)を妻にしたいとはるばる出かけて行き、戸の外で次のような歌を詠った。
以下意訳である。
この本州の隅々まで妻を求め歩いたが、この高志の国に麗しい人がいると聞いて何度も通ったがまだ家に入ることもできず、寝屋の戸を引きあぐんで立っている。
その間に夜はふけて、山のほうでは鵺が鳴いている。野原からは雉の鳴き声が響いてくる。
庭で飼う鶏さえ夜明けを告げ始めた。なんという怨めしい鳥どもだろう。自分も死んでしまおうから、道ずれにこの鳥どももいっそ殺してしまいたい。
幕末、長州藩の高杉晋作のうたった「三千世界のカラスを殺し、ぬしと朝寝がしてみたい。」の原型ではあるまいかなどと想像してしまう。
それでも姫は寝屋の戸を開こうとはせずに次のような歌をうたった。
そのように言われますが、わたしはか弱い処女(おとめ)にすぎません。あなたがお呼びになっても出て会われましょうか。
私の心は浦の渚に住む鳥で、今も立ち騒ぐ波の上を、心乱れて飛ぶ千鳥のようですが、いつかは凪いだ水の上で物思いに浮かぶこともございましょう。
いつかはあなたに抱かれる鳥になるのですから、その恋のために命をお捨てになってはなりません。
続けて、
青山に太陽が隠れ、ぬばたまの夜になれば寝屋の戸を開いてあなたをお迎えいたしましょう。
あなたは嬉しげな笑顔でお出でになり、𣑥(たく)の皮の緒綱のような白い腕で、淡雪のように柔らかな私の若々しい胸を抱きしめ抱きしめて、玉のようなあなたの手と私の手を互いに取り合って枕として、足を長くうち伸ばして、安らかに寝ましょうものを、どうぞそんなに夢中になって恋焦がれないでください。
なんとおおらかで屈託のない当時の恋愛の形がここにある。
これが新潟県にまつわる唯一の話である。
15、須勢理姫の歌
オオクニヌシノミコトの正妻の須勢理姫は嫉妬心が強かった。
当時の人々は何かにつけて歌を詠んだ。そのなかで「ソニドリの 青き御衣を …」とある。これはカワセミの羽のように青い着物を…」となり、この時代も美しい青いカワセミが珍重されている。
同じ歌に、「山がたに 求(ま)ぎし 茜つき 染木が汁に 染めし衣を …」山に捜し求めた茜草の根をついて、染草の赤い汁で赤く染めたこの着物を …」
染色の技術も進んでいていろいろな技術が存在していたことがわかる。
16、海からくる神
オオクニヌシノミコトは岬にいると、沖のほうから、「ががいも」を二つに割れたのを船にして、「みそさざい」の皮を丸剥ぎにしたものを着物にして次第に近づいてくる小人のような神があった。
名前を聞いたけれど答えない。お付の神々にも聞いたけれど誰も知らない。
そこへ「ヒキガエル」が現れて「それは案山子(かかし)のクエビコが知っているでしょう。」と答えた。
このスクナビコナノカミは高天原にいるカミムスビの母神の子で指の股からこぼれ落ちた子であったので、母神はアシハラシコノミコと兄弟となってこの国をつくるように命じた。
このあと、オオクニヌシの子供が生む子の名前に韓神(カラノカミ)や新羅の地名をとったソホリノカミなどの名前がみえる。
古くから朝鮮半島との交流があったことがうかがい知ることができる。
17、高天原の使いたち
地上の葦原中国(あしはらのなかつくに)は大国主命が出雲にあって治めていてその勢力は大きくなっていった。
天の高天原ではアマテラスが自分の御子にその国を治めさせようと考えた。
そこで、何人かの使いを出して交渉するんだがことごとく頓挫してしまう。
そこで、雉名鳴女(キギシナナキメ)という雉を使いに出すことにした。
雉のナキメは天から地上に舞い降り、桂の木に止まってアメワカミコという使いに天の命令を一言漏らさず伝えた。
すると召使の巫女がこの鳥は鳴き声がひどく不吉だといったのでアメワカヒコはさっそく射殺してしまう。
その矢は雉の胸を貫き、空高く射上げられて高天原まで届いた。
その矢を見たタカミムスビノ神はその矢を元来たところ目がけてつき返したところ、寝ていたアメワカヒコの胸板に当り、たちどころに死んでしまった。
ここから還り矢はきっと当たる。という諺ができた。そして、雉の使いは行ったきり帰らぬという「雉のひた使い」という諺もできた。
縁者は嘆き悲しみ、河のほとりに住む雁を岐佐理持(きさりもち)に、鷺を掃持(ははきもち)に、翠鳥(かわせみ)を御食人(みけびと)、雀を哭女(なきめ)とし、八日八晩、死者の霊を慰めるために歌い踊った。
当時の葬儀にも朝鮮半島の影響を受けていると思われる役割があったことが伺える。
19、朝日のただ射す国
大国主命が地上の葦原中国をアマテラスに譲り、天上のアマテラスの孫のアメニギシクニニギシアマツヒダカヒコホノニニギノミコトが天孫降臨して地上の高天原に降りることになった。
このヒコホノニニギノミコトの母は、蜻蛉(あきつ-カゲロウのこと)の羽のように薄い織物に例えたヨロズハタトヨアキズシヒメノミコトという。
御子は天神(あまつかみ)より詔を受ける。
「この豊葦原の、水穂の国は、汝の治めるべき国であると、その役目を委ねられた。この仰せによって、天より地に降りるべきである。」
一緒に下界に降りた部の族の長の一人であるアメノウズメノミコトは伊勢の国に帰り着き、海にいる魚という魚に天神(あまつかみ)の御子にお仕えすることを誓わせた。
ところが海鼠(なめこ)だけが返事をしなかったのでミコトは、紐のついた小刀でその口を裂いてしまった。
それゆえ、今でも海鼠の口は割けているのだという。
それ以来、のちの志摩の島々の国から海で捕れた初物を朝廷に献上するときに、アメノウズメノミコトの子孫にも分け下されるのである。
20、木花之佐久夜姫
天孫降臨したヒコホノニニギノ命は、笠沙の岬でみめ麗しい乙女に会った。名をコノハナノサクヤヒメという。
誠に美しい名前である。
桜の花の咲き匂うように栄えますようにとうけいの誓いをたててニニギノ命に嫁いでくる。
このサクヤ姫が生んだ子供が、海佐知毘古と山佐知毘古である。
海幸、山幸の物語が伝わる。
ここでは、植物では桂の木。海に住むものではアシカ、鯛、和邇(わに)が登場する。
22、豊玉姫の歌
山幸彦であるホヲリノ命は、兄の海幸彦の釣針を探しに綿津見の海神の宮殿に行き、そこに住むトヨタマ姫を妻にして子供を生むことになった。
海辺の波打ち際に、鵜の羽で葺いた屋根の産屋を造り、夫にはお産の様子を決して見ないよう頼んだ。
にもかかわらず不思議に思ったホヲリノ命はこっそり見てしまう。
すると、妻の身体は八尋もある恐ろしいワニに変じてお産で苦しんでいる姿がそこにあった。
驚いて逃げる夫にトヨタマ姫は恥ずかしく思い、生んだわが子を残して生まれ故郷に帰ってしまった。
このとき生まれたのが、アマツヒダカヒコナギサタケウガヤフキアヘズノミコトという。
そして、この御子が結婚して生まれたのが、初代天皇となる神武天皇(カムヤマトイハレビコノミコト)となるのである。
古事記 中巻(なかつまき)
23、東への道[神武]
神倭伊波礼毘古命(カムヤマトイワレビノミコト-後の初代神武天皇)は兄と共に、日向の国の高千穂の宮で国を治めていた。
天下を安らかに治めるためにもっと東のほうへ行こうということになった。
筑紫、安芸、吉備と東進して行くと速吸門(豊後水道)で亀の甲羅に乗って釣りをしている人に会う。
さらに登美の地においてナガスネビコと戦い、そこで兄が戦死する。
やがて熊野の村に入ると巨大な霊力を持った熊のためにカムヤマトイワレビコノ命一行は正気を失ってしまい寝込んでしまう。
この危機にアマテラスが霊剣をつかわしたところ、剣を使う前に熊は切り倒されてしまう。
さらに、天神から案内役として八咫烏がつかわされた。
吉野川の河上に達すると、割竹を編んで筌(うえ)で漁をしている者に会う。これが阿陀の鵜飼の部の祖先である。
現代では八咫烏は日本男子サッカーチームの旗印になった。
24、征旅の歌
吉野の道のない深山を踏み越え道を穿って宇陀に着いた。そこで戦いの後イワレビコノ命が詠んだ歌に「宇陀の 高城に 鴫罠はる … いすくわし 鷹(くぢ)ら障る …」
「いちさかき 実の多けくを …」 とある。
また、忍坂の大室では勇猛な八十人の一族が住居の穴のなかで蜘蛛のように潜んで待ち構えているところへ計略を持って討ち取るための合図に詠んだ歌がある。
さらに戦死した兄、イツセノ命の弔い合戦のときにイワレビコノ命の詠った歌に「みつみつし 久米の子等が 粟生には 臭韮ひと茎 …」と詠っている。
また、「みつみつし 久米の子等が 垣下に 飢えし薫(はじかみ)口疼(ひび)く …」ハジカミとは山椒の木のことである。
そして、「神風の 伊勢の海の 大石に はひもとほろふ 細螺(しただみ)の …」シタダミとはささごのこと。
この項では六首の歌が詠まれているが、そのうちの四首に動植物の名前がみえる。
25、七乙女
カムヤマトイハレビコノ命は正式の大后を求めていた。よく晴れた日の丘の上に七人の乙女たちが野遊びをしていた。
通りかかった天皇に連れのオホクメノ命が天皇の気持ちを聞いた。このなかの誰がよいですか。と直接聞くのではなく歌で尋ねている。
「倭の 高佐士野を 七行く をとめども 誰をしまかむ」
天皇はそのなかのイセケヨリ姫を指名。するとオホクメノ命はその旨を姫に告げた。
武勇を誇るオホクメノ命は目尻に刺青をしていたのでそれを見て姫が詠んだ歌が「あめつつ 千鳥ましとと などさける利目」
雨燕(あまどり)、ツツドリ、千鳥、螐鳥(しとと)などのようになぜそんな恐ろしい眼をしているのですか。と詠うのである。
言葉を直接ではなく歌にして相手に対する気持ちを伝える。
現代のメールやインターネット時代よりずっとスマートで優雅ではないか。
姫は天皇の意を汲み狭井河のほとりの姫の家で一夜を共にした。
この河のほとりには山百合草が多く咲いていた。
そこで山百合の元の名であった「佐葦(さい)」から狭井河の名前になったという。
この項で神武天皇は亡くなるのだが、その年百三十七歳だったという。
稜は畝傍山の北、白檮の樹(樫の木)の生茂った山裾のほとりにある。と記されている。
古事記では、神話の世界から神武天皇が大和朝廷を成立させるまでは、生き生きとした人間性に富んだ挿話が多く記されている。
その後は、歴代天皇の系図が中心となり、具体的な出来事の記述は少なくなっている。
≪続く≫
- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)
a:10619 t:1 y:2