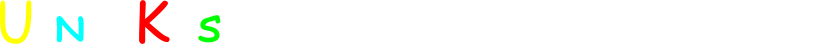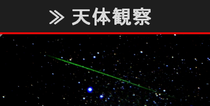仏教の歴史-1
■ 仏教の歴史-1 (仏陀の誕生から大乗仏教が興るまで)
2013年4月20日(土)
- インド 鹿野苑 現在のサルナート
釈迦の出現
お釈迦様が実際に存在したことが証明されたのは、今からわずか百四十五年前のことである。
それは日本が明治維新を迎えたちょうどその年のことであった。
1868年、イギリスの考古学者フェラー博士がインドにおいてルンビニーの遺跡を発見した。
そこで出土した一本の石柱の表面に鮮明な文字が刻まれていた。
「アショーカ王は、即位灌頂の第二十年、自らここに来り、親しく参拝した。ここでブッダ=シャカムニが生誕せられたからである。それで石で馬像を造り、石柱を造立せしめた。ここで世尊が生誕せられたものを記念するためである。
ルンビニー村は租税を免除せられ、また生産の八分の一のみを支払うものとする」
この碑文により、この地が仏陀生誕の地であることが判明し、釈迦が実在したことが、ここに初めて証明されたのである。
そして、歴史書の存在しない古代インドにおいて、紀元前三世紀に建てられたこのアショーカ王法勅の碑文がインドにおける最古の文字記録でもあった。
釈迦の誕生
今から約2500年前、前六世紀頃のインドでは、都市と呼ばれるものが出現していた。
この時代に貨幣経済が発展し、商工業が生れると同時に多くの都市が生まれ繁栄したのであるが、王政をしく群小国家もまた互いの勢力を競う覇権争いの時代に入っていた。
釈迦は、インド、ネパール国境沿いのテライ地方にあった小国カビラバストゥ(Kapilavastu)を支配していた釈迦(Sakya)族の王シュッドーダーナ(浄飯王)と、その妃マーヤー(摩耶)の長男として誕生する。
両親にとって結婚20年目のことであったという。
母のマーヤーがある夜、夢の中に白像が右の脇から胎内に入るのを感じて懐妊する。
出産のため実家に帰る途中、花咲くルンビニー園に入り,アショーカの樹(無憂樹)《一説ではプラクシャ(イチジク)の樹 》を右手でその枝をつかんだとき、右脇から釈迦が生れた。
インドでは右が清浄と考えられていたことからこのように伝えられた。
誕生日はインド暦バイシャーカ月(5月末から6月始め)の満月の日とされ「ベーサカ祭」としてセイロン、東南アジアに伝わった「南方仏教」では前1世紀より盛大に行われている。
中国、日本に伝わった大乗仏教では釈迦の誕生を4月8日としている。
釈迦の幼名は釈迦族の姓であるゴータマ。名をシッダッタ(悉達多)と名づけられた。
姓のGotamaは「最も優れた雄牛」の意味で、インドにおける動物崇拝、特に牛に対する崇拝の観念と関係している。
名はサンスクリッド語ではSiddhartha(シッダールタ)「目的を達成する者」を意味する。
生まれたての釈迦が七歩歩いて「天上天下唯我独尊」と言ったとされている。
これは後代,釈迦の神格性が高まり仏伝となって伝えられたものだ。
当時の習慣であった七日目の命名式に、生れた星の吉凶をアシタ仙人に占ってもらったところ、将来は偉大な王となるか、偉大な宗教者になると予言された。
しかし、産後のひだちが悪かった母とは生後七日目で死別する。
釈迦は継母となった叔母(母の妹)マハーブラジャーバティーに育てられ、跡を継ぐことを願う王からはカピラ城での何不自由のない生活を与えられ育てられていった。
当時のインドの宗教はバラモン教でベーダ聖典を奉じた自然界の多神崇拝の宗教であった。
祭祀など宗教儀礼を民衆に規定し、司祭者であるバラモンによってカースト制度という厳しい身分制度の社会秩序を作り出してきた。
以前の農耕社会にあって最上位を保持してきたバラモンも、この時代では王侯が最上位を占めるようになり、商工業者が多数のギルドを形成し、豊かになってきていた。
バラモン教の気風や習慣といった旧来の文化は廃退化の傾向が進み、民衆は高度成長期の中で物質的な豊かさを求め、道徳的廃退が蔓延してカースト制度も崩壊し始めるという社会の変動期にあった。
そんな時代の転換期にあって、インド社会ではバラモン教の権威を否認して、新たな価値観を求める自由思想家も多く現れるといった世相を呈していた。
釈迦族の住む、現在のウッタルブラデシ地方は北にヒマラヤ山脈,南にはガンジス川に注ぐ多くの支流があり、豊かな水利による米作が中心の共和制国家であったが、主権は隣のコッサーラ国のもとにあり、やがて釈迦が出家した後、その隣国によって滅ぼされる運命にあった。
こうした時代背景のなかで、王子として何不自由なく享楽的な生活をしていた釈迦であったが、自国の命運も敏感に感じ取りながら育ってゆくなかで、次第に物思いにふけるウツ的な性格となっていく。
ただ、文武にわたって際立った能力を示していて、妻を選ぶにあたって従弟のデーバダッタ(提婆達多)などと武芸を競って勝ち、いとこのヤシューダラーを后に選んだとされている。
こういうことは当時の風習で、よくあったとされているが、釈迦の伝記では青春時代の記述が一番遅くに成立している。
いずれにしても、釈迦の性格は変ることはなく苦悩は日増しに深まりゆくばかりであった。
そこに、有名な「四門出遊」の話が残る。
ある日釈迦が城の東門を出ると、杖をついてよぼよぼ歩く白髪の老人に会う。人間は否応なく老いてゆく。
次の日、今度は南門から出て歩いて行くと、今にも死にそうな悲壮な病人に出会う。人間は病という不安をかかえて生きている。
またある日に、西の門から出て行くと、嘆き悲しむ死者の葬列に出会った。生を受けたときから死は約束された人間の宿命ということを知る。
最後に、北門から出ると、静かに歩く一人の沙門(修行者)を見た。
その出家修行者の円満な容貌を見て、これこそ自分の理想であるとして出家の決心を固めるのであった。
(『ジャータカ』より)
これも後代の伝説として、釈迦が人生の苦悩を強く抱いていたことを示すと共に、出家を誘導的に暗示するために記されたものと思われる。
結婚して数年後にして一子「ラーフラ」(羅ご羅)が生れるや、「ラーフ(障害、悪鬼)が生じた、繁縛が生じた」と言ったので「ラーフラ」と名付けたと経典にある。
また、ラーフは竜の頭を意味しており、ラーフラとは「ナーガ(竜)の頭になる者」、つまり跡継ぎが生まれたことを歓喜した釈迦が名づけたという説がある。
恵まれた環境といえども釈迦族の政治的立場の不安定さや人間相克のなかにあって、たえず心中の不安は消えず、釈迦も子供の誕生を機に出家を決心する。
跡継ぎの生長を待って出家するという風潮は当時そうめずらしいことではなかった。
その夜、宮殿を出ていく前に幼い愛児に最後の別れを告げようとして妻の寝室に入る。
釈迦は深い眠りについている二人をただ眺めるだけで、意を決してその場を去り、愛馬カンタカと馬丁チャンダカを従えて城を出ていくのであった。
突如として残された妻ヤシューダラーの嘆きと恨みが仏伝に残る。
「私は二十九歳で善を求めて出家した」と後に釈迦自らが語っている。
悟りに至る道
釈迦が城から出奔して最初に教えを求めたのは、瞑想に専念している行者、アーラーラ・カーラーマという仙人だった。続いてウッダカ・ラーマブッダのもとを訪れる。
世界が有限か無限かなどの議論や、体と霊魂は同一か否かといった人生問題の解決に直接役立たない形而上学的問題についての論議は益がないとして、そのような対立的な見解にとらわれず、真実の生きる道をさぐろうとして瞑想に専念する彼らの修定主義を否定していった。
やがてヒンズー教の聖地であるネーランジャラー川のほとりのウルベーラー付近の森に入り、修定主義から苦行主義へ転換した釈迦はここでの回想を多く残すこととなる。
そのなかで悪魔との問答が数多く出てくる。
そこには伝統的なバラモン優位の習慣や、旧来の思想や煩悩との対決など精神的な葛藤がみられる。
悪魔は釈迦自身の他の一面の象徴であり、誘惑に勝つには誘惑の中で対決してこそ退けることができる。と釈迦は語っている。
こうして苦行は六年間続いた。その身体は皮と筋だけに削ぎ落とされ極度の痩身状態になったが結局目的を果たすには至らなかった。
ウルベーラーのセーナーニー村の娘「スジャーター」が釈迦の風貌に、樹の神の出現と信じ、乳糜(牛乳に水洗いした米を入れ煮て砂糖をいれた流動食)を供養した。
釈迦がそれを摂るのを見た一緒に修行してきた五人の仲間達は、彼は貪り、努め励む修行を捨てたとしてこれを嫌い、釈迦のもとを去ってしまっている。
釈迦は、人生の矛盾を契機に悩みをいかに解決するかということから修行を始めた。
しかし、いくら瞑想しても、絶食などの苦行をしても解決の糸口は得られなかった。
それでは単に人生逃避のための思索であって何らの問題の解決にはならないことを知り、その結果をもとに現実生活の中で不安を解消する努力が最も必要だということを感じとっていくのであった。
悟り
釈迦もウズベーラを去り、次にたどり着いたブッダガヤー(Buddhagaya)のネーランジャラー河畔のアッサッタ(アシュバッタ)樹のもとで瞑想に入った。
七日後、釈迦 35歳 の12月8日、明けの明星を眺めながら、ついに悟りを開くことになる。
このアッサッタ樹が後に「菩提樹」と呼ばれることになった。
悟りの内容を世間に説くのをためらっている釈迦の前に、インドの最高神である梵天(プラフマー)が現れて、速やかに説法することを勧めた。
これが梵天勧請の伝説である。
そこで、悟った内容を整理するためにさらに七週間,瞑想にふけった。
釈迦は自分の悟った法をベルナスに去った五人の仲間に伝えるべく、250Kmも離れたベルナスの郊外にあるミガダーヤ(鹿野苑-現在のサルナ-ト)まで行き、いぶかる彼らの前で初めて法を説いた。
これを聞いた五人の元の仲間達も釈迦と同じ境地を悟り、即座に五人とも釈迦の弟子になったという。
これが「初転法論(しょてんぼうりん)」である。
ここに、仏(教主),法(仏の教え)、僧(サンガ-弟子の集団)の三宝がそろったことで、仏教として成立していくことになる。
その悟りの内容とは、四諦と八正道、初期の縁起観であったとされている。
「かくして、私は自ら生ずるものでありながら、生ずる事柄のうちに患いをみて、不生なる無上の安隠・安らぎを求めて、不生なる無上の安隠・安らぎを得た。
自ら、老いるもの、病むもの、死ぬもの、憂えるもの、汚れたものであるのに、老いるもの、病むもの、死ぬもの、憂えるもの、汚れたもののうちに患いあることを知り、
不老、不病、不死、不憂、不汚 なる無上の安隠、安らぎを求めて、不老、不病、不死、不憂、不汚 なる無上の安隠、安らぎを得た。
そして、私に知と見が生じた。我解脱は不動である。
これは最後の生存である。もはや、再び生存することはない」(中部 二六)
インド語では強調するとき同じ言葉を繰返す特徴がある。
釈迦はここに人間の理法を悟り、そこから四十五年におよぶ伝道の間に成熟し、体系化されていく。
それは固定した観念としてではなく、現実の生活に即して展開することを認めていた。
このことは、思想的発展が無限にあるということであり、仏教の成立時より、その思想が後代の思想家や哲人達によって多様な発展を遂げるという必然性を持っていたことになる。
釈迦がカピラ城に帰国して、孫陀羅難陀、息子の羅ご羅が弟子となった後、釈迦族の諸王子がこぞって仏弟子となり、一族の青年5百人が出家することになった。
釈迦は弟子を連れて伝道の旅に出る。
「ひとつの道を二人して行くことなかれ」と説き、それぞれの弟子も伝道の旅に出し、釈迦自らも何人かの弟子を連れて「沙門」として遍歴したといわれている。
やがて法の体系が洗練されていくに従い、多くの信者、弟子を得ていった。
釈迦の十大弟子
智慧第一の「舎利弗」(舎利子、サーリブッダ) 般若心経で仏の相手として登場する。
神通第一の「摩訶目か連」(目連、モッガラーナ) 舎利子と共に釈迦の弟子になる。餓鬼道に落ちた母を救うため行った供養が盂蘭盆会の起源になったといわれる。
(釈迦の最も信頼の厚かった二大弟子と呼ばれたこの二人は早世している。)
頭陀第一の「摩訶迦葉」(大迦葉、マハーカッサバ) 釈迦の死後、仏教教団の後継者となる。
空の解釈の第一人者「須菩提」(しゅぼだい、スブーティ) 無諍第一。被供養第一ともいわれた。空を説く大乗経典にしばしば登場する。
説法第一の「富楼那」(富楼那弥多羅尼子、ふるなみたらにし) 十大弟子中では最古参。
論議第一の「摩訶迦旃延」(まかかせんねん) 受戒には三師七証が原則。辺地では五人でも可とする許可を仏陀から得、仏教伝道において重要な働きをした。
天眼第一の「阿那律」(あなりつ、アヌルッダ)釈迦のいとこ、仏の前で居眠りをして叱責を受け、眠らぬ誓いを立てたが視力を失う。それがかえって真理を見る眼を得たとされる。釈迦の従弟。
規則第一の「優波離」(うばり、ウバーリ) 教団の実践規定集「律」を編集する。
蜜行第一の「羅ご羅」(らごら、ラーフラ) 釈迦の息子。最初の少年僧(沙弥)となる。学習第一とも称せられた。
多門第一の「阿難」(あなん、アーナンダ) 釈迦のいとこ。釈迦の説いた「経」を編纂する。「如是我聞」の「我」とは多くが阿難であるとされる。釈迦を説得し女人の出家を認めさせた。摩訶迦葉の跡を継いで仏法付法蔵の第3祖となった。
また、信者にはインド最初の統一王朝マガダ国王「ビンビサーラ」やコーサラ国王「プラセーナジット」、その首都に建てた祇園精舎(祇陀林給孤独園)を寄進した豪商「スダッタ」などがいて、多くの僧院、僧堂が建立されていった。
無名に近かった釈迦を一躍有名にした話が残る。
マガタ国の国王に深い帰依を受けていた、優楼頻羅迦葉(うるびるばーかしょう)、那提迦葉(なだいかしょう)、伽耶迦葉(がやーかしょう)の三兄弟(三迦葉)がそろって釈迦に帰依した。
彼らは火を用いて神を祭り、様々な神通力を行い、千人もの弟子を持つほどの有力者であった。
ある日、釈迦は長兄の優楼頻羅迦葉の家で一泊する。
その宿坊は火を祀るお堂で、そこに住む竜は、迦葉の言うことは聞くが他のものには害を与えるといわれ、また、別の経典では恨みを抱いて死んだ修行者の亡霊だとしているが、釈迦は、この火を吐く竜を自ら火界三昧により折伏し鉄鉢のなかに閉じ込めてしまう。
この話は、大乗小乗の経典に詳しく記されていて、サンチー大塔の彫刻など、他の史跡にも多く残されている。
釈迦自身も神通力を備えていたとする逸話である。
釈迦は他の沙門にさきがけて集団生活を実践する。それを「サンガ」(教団)と呼んだ。
当時厳しいカースト制度の身分制度社会にあって、身分に関係なく、出家,戒律を受けた順に上座に据えた。
この平等主義は釈迦の理想としてのカースト社会批判からでてきたものである。
さらに,アーナンダの尽力で女性の教団を設け、男性の出家者をビク(比丘)と呼んだのに対し、これをビクニー(比丘尼)と称した。
それに在家の男女の信者はウバーサカ(優婆塞)とウバーシカー(優婆夷)という仏教信徒とし、ここに四衆の構成が成立した。
このような高い理想をもった仏教という組織ができたことは、厳しい身分制度が確立していた古代インド社会においては特筆すべきことであった。
以後、釈迦は四十五年間にわたり、八万四千におよぶ法門を説いていく。
その数の信憑性はともかく膨大な教えを残した。
そこには、この世における生死の無限の苦しみから逃れる道を開き、いかなる権威にもとらわれることなく、人が人として正しく生きるべき道が説かれていた。
ここに釈迦は「仏陀」と称されることになり、仏教の開祖となったのである。
釈迦入滅
八十の老齢になって、生涯の終わりを感じた釈迦は、首都ラージャガハを出て生れ故郷に向かい最後の旅についた。
途中、鍛冶工チュンダの供養の食べ物が弱っている釈迦に激しい下痢の症状を起こさせた。
クシナガラ(Kushinagara-現在のカシアー)までたどり着くと、「私のためにサーラ樹(沙羅双樹)の木の間に、頭を北に向けて床を敷くよう」と頼んだ。
最後まで付き添ったのは、いとこのアーナンダと同アルヌッダである。
「アーナンダよ。私は疲れた。横になりたい」といいながらも最後まで法を聞きたいと願い悲しむ人々のために法を説いた。
そして安らかに息を引き取ったのである。
その日は満月であったとされている。
釈迦の最後を記した経典の描写はアーナンダの悲嘆をして極めて印象的である。
「法をよりどころとせよ、自己自身を灯明(よりどころ)とせよ。私に頼らずあなた方自身で生きよ」「すべては移ろいやすい、怠らず務め」「出家者は私の葬儀に関わるな。
葬式は在家者がするであろう。私が辿った場所には人々が集まるであろう」という遺言が残された。
死に際して自分を偶像化するなとも言い残している。
旅の途中で入滅したことも仏陀の教えの根本が示されている。
釈迦自身も怠ることなく修行を続けた。すべては移ろいゆく無常のものである。
その修行の完成が死を迎えることにより、それが悟りの本源となることを自らの生き方によって示したといえる。
クシナーラ(クシナガラ)から東へ1,5km離れた所に、釈迦が荼毘にふされた「ラマバル」という塚が残る。
遺骨は当時の有力な部族や王によって八つに分配され、それを祀るストーパ(塔)がそれぞれの地に建てられた。
それを管理したのが釈迦を信奉するその地域の人達であった。
釈迦の死没年が、紀元前483年、前383年説や南方仏教圏では前543年と定かでないが、80歳で没したことは定説となっている。
当時の文字を持たないインド社会においてそこまでわかっていること自体かなり驚異的なことだとされている。
仏典編纂
釈迦の滅後、早速、釈迦の教えが散逸しないよう、そして正確に留めるため、「摩訶迦葉」(マハーカッサバ)は五百人の正統な弟子を選び、マガタ国ラージャガハの郊外の「七葉窟」で「第一結集(けつじゅう)」となる仏典編纂を行った。
このとき集まった五百人の弟子のことを「五百羅漢」と呼ぶ。
まず、多聞第一の「阿難」(アーナンダ)が釈迦の言葉を口述し、経のひとつひとつを唱え、全員の賛成を得て「経蔵」が編纂された。
教法はすべて口誦によって伝承されたので私は仏陀から間違いなくこう聞きましたとして権威づけるため「如是我聞…」で始まるのが経蔵の特徴である。
これは後代、漢訳で五つの「阿含経」の集成書として残る。
次に、規則に詳しい「優波離」が口誦する律の条項のひとつひとつに賛成を受け「律蔵」として教団の実践規定集が編集された。出家者、男女の僧それぞれの戒律箇条を設けている。
ここにおいて、「経」(sutra)と「律」(vinaya)が正式に制定された。
少し遅れて、有能な教義学者たちによって「論蔵」が制定されていく。
経と律、特に経に対して施された注釈文献集である。
「上座部」が仏陀の教説を理解したところの解説を示し、上座部による釈迦の考え方の正当性が明示されたものである。
(上座部とは戒律を厳格に尊守することを主張した保守的な長老上座の出家修行者達の学派 )
経は「線」「たて糸」の意味をもつ。当初は教法を圧縮してまとめていた。
当時は記憶による伝承しか方法がなかったからである。
それに次第に説明が加えられ、長文の経典も作られてゆき、集大成して「経蔵」となっていった。
この経蔵、律蔵、論蔵を「三蔵」と呼び、漢訳では「一切経」また「大蔵経」に網羅する。
最終的には一万巻を越える大叢書に増広していく。
後世において、これらの三蔵のすべてに精通した僧に「三蔵法師」という称号がつくのであるが、有名な唐の玄奘三蔵の他にたくさんの三蔵法師が出現していくのである。
釈迦の教え
釈迦の悩みは生を苦しいと思い、死を恐ろしいと思う不安を本来のありかたとする人間そのものの姿と対決するために出家した。
当時の思想界は世界が有限か無限か、如来(覚者)は死後に生存するかしないかといったような形而上学的な束縛のなかでの苦行,修行であって、そのような思惟から開放し、生への追求に必要なものを取り上げることで人間実存の解脱の道を実践していこうとすることから釈迦の思想は出発していた。
【 四諦(したい)・八正道 】
「人間はどこにあっても、またいかなるものによっても、苦から脱することはできない」(『ダンマパタ』189)
「何人も老い、かつ死ななければならない」(『ダンマパタ』286、287)
人間が固体を有しているところに苦の根源があり、これは定まった理法である。ここに「一切皆苦」として人生を実践的立場から説いた「四諦」(四つの真理)としての命題が出される。
苦諦-生老病死も愛憎や別れ、求めるものが得られないという執着は皆苦である。
集諦(じったい)-その苦悩の原因が人間の執着にあるという認識。
滅諦-理想世界を設定し、その境地に至るためには苦悩を消滅しなければならないという認識。
道諦-理想に達する正しい方法。
この滅諦と道諦が特に重視され、その実践の規範として「八正道」が説かれた。
「八正道」とは、正見(正しい見解)、正思(正しい思惟)、正語(正しい言語行為)、正業(正しい行為)、正(しょう)命(みょう)(正しい生活)、正精進(正しい努力)、正念(正しい理念、目標)、正定(正しい精神統一) のこと。
これは、従来の神秘的直感を重視したバラモンや苦行を力説した行者と異なり、道徳的規範を実践することによって理想世界に到達しようとするものであった。
【 縁起観 】
縁起説の基本形式は「これがあればかれあり、これなければかれなし、これ生じるがゆえにかれ生じ、これ滅するがゆえにかれ滅す」(『スッタニパータ』12,34)
縁起とは「縁りて起こること」で他と関係して起こる現象界のあり方である。
いかなる条件や原因によって苦が生じ、また滅するかという人生の苦悩や不安を解決するための考え方として「縁起」という観念があった。
すべての存在は独立した存在ではなく、常在不変でもない。相関関係において相互に依存している。
そこから「十二縁起」(十二因縁)がまとめられた。
十二縁起とは、人間がたどる人生の過程において必然的におこる因縁で、「無明」(根本である心の無知)-「行」(潜在的な形成作用)-「識」(識別作用)-「名色(みょうしき)」(固体=名称,形態)-「六入(ろくにゅう)」(六種の知覚)-「触」(接触)-「受」(感受)-「愛」(盲目的な妄執)-「取」(執着)-「有」(生存)-生 -老死。 の連続した関連をいう。
「無明を縁として行あり、行を縁として識あり、識を縁として名色あり、ないし、生を縁として老死あり」と苦悩の過程を原因と結果について観察する。
また、その逆に結果から原因へと観察して本質を究明すると同時に、「無明,滅するに縁って行,滅す。行,滅するに縁って識,滅す。ないし生,滅するに縁って老死,滅す。ゆえに憂悲愁苦悩滅す」という思索の過程を示す。
これは相生と相克の関係である。
ここでは人生の苦悩は「執着」にあり、執着は生存に対する盲目的妄執(渇愛)に依存しており、妄執もひいては無明に依存していることを説く。
この「縁起観」が初期の釈迦の説教には様々な形で示され、後世の仏教思想はこの「縁起思想」を基にして、展開し発展していったものと思われる。
( 2001年タリバン政権が破壊したバーミヤン遺跡(5-8世紀造営)の高さ約38mの東大仏立像の残骸の中から胎内経が発見された。そこに「縁起経」の原典の冒頭部分が読み取れた。玄奘三蔵もここに立寄り「大唐西域記」に記している。世界遺産。)
【 無我と自我 】
「自己を愛するものは他人を害してはならない」(『スッタニパータ』1.74)
自己を愛すると同じく他人の自己も尊び、さらに実現される自己の充実を他人と協力することでその充実を望むものであると説いた。
「無我」とは実体のない性質のことである。
生存は五種の感覚とその対象、さらに素質、衝動、本能、生命力の造形的な力など、無意識的な形成力と意識から合成されているが、死によってすべてが解体する。
それらの中にその中心となる我は有さない。
釈迦は現実性と倫理性を加え、主体としての自己を鍛錬してはじめて真の自己にいたると主張した。
それは自己の探求から批判的反省をへて無我説が展開され、決して他者との関係を軽視せず、慈悲の精神を強調することで自己に対する激しい執着と葛藤を凝視し、そこから脱却しようと努力することが釈迦の教えの原点であった。
【 法・涅槃 】
以上のような思索の過程を経て、仏教の根本原理となる「諸行無常」「諸法無我」「涅槃寂静」という三つの真理、「三法印」が説かれた。
「諸行無常」はあらゆる事象は移り行き流転するという現実世界の認識である。
そこから「一切皆苦」「諸法無我」という考えが展開してくる。
インドでは法(dharma)は慣習、風習といった行為の規範から人倫の秩序、宗教的義務の意味まで広い意味を持っていたが、釈迦はふたつに大別して説いた。
「諸法無我」とは、諸法はあらゆる事象、存在であり、現実世界に存在するものの集合としてとらえ、すべての存在は我というような形而上的実態を持たないことである。
それに対し、普遍的客観的真理も法という語で表現した。
仏がこの世に出現しなくても永遠に変ることのない真理であり、たまたま釈迦がこれを発見したにすぎないとした。
「縁起を見る者は法を見る。法を見る者は縁起を見る」(『中部』1.26)
現実の苦悩を凝視して煩悩の起こらない状態に至れば、生存への執着が去り、輪廻に支配されない自由な境地に到達できる。それが「涅槃」(mirvana)である。
「涅槃寂静」の「涅槃」とは、煩悩の火が吹き消された状態をいい、苦悩のない状態を意味する。
この静かな心の安らぎこそが真の幸福であるとした。
涅槃は仏教以外でも使われていて、死後においてこの境地に達するとされていたが、釈迦は、この理想の境地は生きている間に人格を形成し、自由に活躍し、また周囲に対しても不安のない永遠の平安の境地をつくりあげるよう努力することであると説いた。
人生の不安を意識したところから、理想を意識し追求しようとする姿勢は、当時一般的に行われていた形而上学的な苦行とは異り、理法による人倫的行為を通して理想の境地に向かって努力しようとしたところに釈迦の仏教の出発点としての意義があった。
宗教倫理
「もろもろの悪をなしてはならない。すべて善いことを行え。自らはその意を清める。これが諸仏の教えである」
自己の心情を清浄にすることによって、煩悩のけがれを清めようと努力する。これが仏教の実践的要求であり、仏教倫理の基本的原理である。
そして、施し(施論)と五戒を守り(戒論)、その行為の結果、優れた境地で幸福な生活が送れる(生天論)という三種の立場で説明し、それは必ずしも来世を待つのではなく、現世の生活のなかで経験できるものであるとした。
あくまでも釈迦の思想の根本は人格完成への理想に進むべき道であり、戒律もしごく当然の規範のなか執着しないという境地からおのずから現れ出た智慧の働きによって完成する。
それは真実の自我による智慧や経験を十分に発揮させよという実践的方法であった。
仏陀の説く「愛」には十二因縁のなかの「渇愛」と、この「慈悲」がある。
「慈」はいつくしみ。真実の友情であり、「悲」はあわれみ。同情である。
釈迦は同じ心情で一切の衆生を愛せよと強調する。さらに全世界に向けて無量の慈しみを起こすべきであると説いている。(『ダンマバダ』43)
そして衆生に対しては仏の眼(あわれみ)をもって世間を見渡している。(『スッタニパータ』1・138)
この慈悲の精神は人々がお互いに助け合って進まねばならぬという気持ちに由来し、理想としては一切の生きとし生けるものに及ぶべきものであると説いている。
これは、般若心経の最後の咒文「羯締羯締波羅羯締波羅僧羯締菩提娑婆訶」に通じていて、宇宙の命、自然の命、あらゆる命への慈悲心を喚起する仏教の理想を示している。
仏陀観の変遷
釈迦の入滅後、帰依者たちによってやがて神格化されていく。
姓のゴータマは使われなくなり、ゴータマ・ブッダから単に仏陀と呼ばれるようになる。
そこから、さらに1,如来(完全な人格者) 2,応供(尊敬される人) 3,正遍知(正しく悟りを開いた人) 4,明行足(明知と実践を具現している人) 5,善逝(幸福な人) 6,世間解(世間を知っている人) 7,無上士(最上の人) 8,調御丈夫(荒くれ男を御する人) 9,天人師(神々と人間の師) 10,世尊(世にも尊い人)と次第に理想的な身体的特色を仏陀にあてはめていった。
仏陀が一段と高い存在として神格化されることにより、法を悟った者は皆仏陀(覚者)となりうるとの考えが生まれることになる。
超人的扱いを受けた釈迦以外にも、釈迦以前に7人の仏陀がいたという過去仏思想が生れ、それらの仏に対する信仰も高まっていくのであった。
やがて、法(ダルマ)そのものが仏陀と同格となり、宇宙の真理も仏陀そのものとして受け取られるようになっていく。
前三世紀のアショーカ王の時代にはすでにこの傾向が明確にみられる。
仏教の転機
釈迦の滅後、すぐに「摩訶迦葉」らにより「第一結集(けつじゅう)」となる仏典編纂が行われた。
さらにそれから、百年も経つと時代の価値観も変わっていく。
その当時に起こった「十事の非法事件」など、ささいなことをきっかけに、自由で進歩的な修行僧たちが旧来の厳格な考え方に対し、戒律の実践をより柔軟な態度で理解しようとする自由主義的な「大衆部(だいしゅぶ)」(マハーサンギカ)をつくり、教団は二つに分裂した。
そのため、保守的な「上座部」〈長老の派〉(テーラバーダ)といわれた釈迦が最初から説かれたとおりの教えとその実践を遵守する正統派としての長老達による学派が三蔵(経蔵、律蔵、論蔵)の教義、実践の純粋性を保つために開かれたという状況があり、七百人の僧を集めて大規模な第二回目の仏典結集が当時の商業都市ベーサリーで開かれた。
ここから「部派仏教」の時代に入ることになる。
その後も「上座部」と「大衆部」の対立は続き、やがて両派ともに分派に分派を重ね、前一世紀頃までに上座部系11部派、大衆部系9部派の《小乗20部》の派が興る。
代表的な部派として西北インドで栄えた「説一切有部」、中西インドの「正量部」西南インドの「上座部」南方インドの「大衆部」があげられる。
多くの部派に分かれたことで、それぞれの派ごとにそれぞれの聖典が編纂されていくことになり、従って共通の聖典というものは存在せず、しかも諸派の聖典はほとんどその後、戦乱や侵略により散逸してしまうのであった。
アショーカ王
前268年頃~前232年頃に統治した、マウリヤ朝第三代の王「アショーカ王」はインド大陸の統一を完成する。(南インドの一部を除く)
そのための戦争は数十万人の犠牲を出すという凄惨なものであった。
これに深く後悔した王は、釈迦が説いた「ダルマ(法)」に基づく政治を決意し、仏教に帰依し、次第に信仰を深めていった。
インドでは古来より「ダルマ」は社会制度から道徳、法律、宗教など広い意味で用いられており、王も人倫の道、社会規範という意味で使用している
この時代は牧畜を中心とする初期のアーリア時代から、ガンジス川流域の農耕中心の社会への発展を見せていた時代で、王は帝国統治の基礎を社会道徳の尊守、狩猟の禁止、お互いの宗教的、思想的立場を尊重し和合することを求めていた。
当時は、ヒンズー教でも仏教でも重要な概念で、解脱を究極の宗教的目標とする共通の認識の中に「ダルマ」という概念があった。
アショーカ王にとって宗教的というより帝国の統治を安定させる支配理念としての意味が強かったものと思われる。
その理想を石柱などに刻ませた。
それが、冒頭で紹介したアショーカ王法勅である。
1868年にイギリスの考古学者フェラー博士が初めて釈迦の存在を発見したルンビニーの石柱もこれであった。
現存するそれらの石柱は15例だけ残る。
仏陀が初転法輪をした地サールナートから出土した背中合わせの四頭の獅子の像は、インドの紋章になった。
ダルマの政治の一環として社会道徳を説き、多くの社会事業を実施したアショーカ王は家父長的な王であったことが偲ばれる。
王は仏教教団を手厚く保護をした。
八つに分配されていた釈迦の遺骨を七つの塔から集め、釈迦の説いた法の数と同じ、八万四千もの仏塔(stupa)を建て遺骨を細分してそこに納め、仏跡を訪れて供養している。
(七世紀、玄奘三蔵の「大唐西域記」にはその当時のいくつかの塔が残っていると記されている。1898年、インドとネパール国境近くで発見されたビブラワーの遺跡の遺骨は、銘文から釈迦の遺骨とされ、名古屋市千種区の日泰寺には、それがさらに分骨されて安置されている。)
アショーカ王の庇護の下、首都バータリプトラにおいて「上座部」による第三回目の「仏典結集」が行われた。第二回結集から、約130年後となる。
インド全土やセイロン、その他諸外国へ正統教義を伝える聖典として編纂され、その直後、各国へ伝道僧が派遣されている。
仏教の大伝道活動を援助したことで、アショーカ王の王子マヒンダ比丘と王女サンガミッター尼がセイロンに初めて伝道使節として仏教を伝えた。
前三世紀、セイロン王デーバーナンビア・ティッサ王(在位前250年~前210年)のときである。
その時、ブッダガヤーの菩提樹の分枝を持参して植え、そこに後のマハービハーラ(大寺)となる精舎を建てた。
これによりセイロンは仏教に改宗し、それ以後のセイロンは初期仏教(小乗仏教)の一大中心地となるのである。
しかし、アショーカ王の死後、マウリア帝国は分裂し衰退していく。
それに伴いダルマの政治も放棄されてしまう。
その後、より伝統的、保守的になっていくインド仏教は、国王,富豪、などの帰依を受け、多くの寄進を受けるようになる。
大規模な荘園を寄進されたり、ギルドに現金を貸し付けたりして教団の維持にあてるなどして教団の組織は肥大化していった。
釈迦が説いた教えは、紀元前後ころまで、四百年以上口踊で伝えられた。
文字化されるまで幾多の言語上の変遷は経ていると考えざるをえない。
釈迦の説教はアーガマ(阿含)といい、セイロンにおいてパーリ語であらわされたので「パーリ聖典」という。
(日本ではこの聖典は「南伝大蔵経」65巻(1935年~41年)として完訳されている。)
セイロンには前三世紀に仏教が伝えられ、初めて文字による記述となるのは前25年頃であると、修行僧「マハーナーマ」が「ダートゥセーナ王」(459年~477年在位)の命を受けて編纂した「大いなる史書」(マハーバンサ‐セイロン)に記されている。
前一世紀後半(前25年頃)になると、セイロンは戦争と飢餓のため国土が荒廃。
その危機感からマハービハーラの僧達は「貝多羅葉(ばいたらよう)」の上に文字で聖典を写す作業をはじめた。
これがインドにおける最初の筆写事業となった。
この文字にして編纂するときに、セイロンにおいて第四回目の「仏典結集」が行われている。
セイロンに仏教が伝えられてから約二百年後のことである。
そのときにできた「パーリ聖典」が、唯一完全な形でインドの言語(パーリ語-古代インドの俗語)で現存する釈迦の思想に最も近い、最も権威ある聖典とみることができる。
それがセイロンを起点にビルマ、タイ、ラオス、カンボジアと東南アジア諸国に伝わり「南方仏教」として、今日でも東南アジアの仏教は「上座部」と称しているのである。
その特徴は、どの寺院でも、菩提樹が植えられており、仏舎利を祭る仏塔が建てられ、涅槃像が安置されている。
これらの三種に釈迦に対する深い思いが込められている。
「説一切有部派」
仏陀の没後三百年が経ち「上座部」から分かれた「説一切有部派」(Sarvastivadim-有部(うぶ) )は分裂した内の有力な派で前2世紀前半から1世紀に成立した。
三世(過去、現在、未来)いずれに存在するものはすべて実在であるとする「三世実有説」の「業感縁起」。それに「百八の煩悩」を考えたのもこの「有部」においてである。
ここでは釈迦は別格の人格者で一般修行者は阿羅漢までしかなれないという思想をもつ。
この教義の発達にともない、仏教は、哲学化し、煩雑になり出家修行者偏重となって、民衆からは難解で独善的になった教団に対する反発が生じるようになってゆく。
また、独自の立場から聖典を編纂して膨大な教義綱要書(阿毘達磨)を作成していった。
「有部」において「発智論」で教理を確立し「六足論」「倶舎論」などを著す。
これらを集成した「大毘婆沙論」二百巻は部派仏教の百科事典のような膨大なものになった。
その聖典は北方インドを経てガンダーラ、カシミールで栄え、中国、チベットに伝わり、その勢力を伸ばしていくことで大きな影響を後世に与えることになる。
やがて、新しい考え方をもって興る大乗仏教でさえその基礎教理をここから借用しているのである。
大乗仏教の萌芽
前百八十年頃、インドではアショーカ王のマウリヤ王朝が崩壊すると、西北方から異民族の侵入が続き、北方インドは異民族の支配下に入る。
紀元一世紀前後には東西諸民族の文化交流も活発となり、その影響で新たな宗教運動が起こった。
その新しい形態が「大乗仏教」という仏教運動である。その成立は前一世紀頃と推定されている。
カースト制度の社会に平等の思想をもって仏教は成立したが、結局インドから北の方角へ追いやられるようにして伝播していくことになった。
その北の方角のガンダーラ地方、今のアフガニスタンの辺りにはギリシャ人がいて、彼らが伝播してきた仏教に興味を持った。
当時このあたりの仏教徒は上座部の分派の「有部」が有力で「仏様というのはひとつの観念であって、言葉であって、姿としては出てこない」としてあえて仏を人間的な形で表現することはなかった。
この伝統を打ち破ったのがガンダーラ美術である。
ギリシャ人にとっては目に見えないものは信じられない。そこで彫刻の名人が多かったギリシャ人はお手本もないまま様々な仏像を造ってしまった。
このガンダーラにおいて初めて仏像がつくられたのである。
ギリシャ人による最初の仏教的作品は階段の蹴込を飾るフレームで、男女数人が蓮華の花束や樹の葉を手にし、供物を入れる容器を捧げる「献花供養」の図柄であった。
次に「祇園布施」の図柄となり、弟子を従えた釈迦が布施の申し出を受納しているもので、釈迦は大衣をまとい口ひげをたくわえ、一際大きく描かれ、小さな頭光をつけている。このころの服装はまだインド風の服飾となっている。
1世紀末には「仏誕七歩行」などの図柄を経て、2世紀初頭になると仏陀の単体像が造られるようになってゆき、釈尊の姿はギリシャ人のような風貌になっただけでなく、ギリシャ・ローマ風の服装、装身具をまとっていた。
さらに仏陀像を小型にしたものが菩薩像として造られた。
アレクサンドロス大王の子孫であるギリシャ系の王国とアショーカ王時代の仏教が出会い、ギリシャ風仏教美術がここに生れたのである。
そのときに造られた仏像が逆にインドに刺激を与えることになり、マトゥラでインド的な仏像が造り出されるようになる。
このガンダーラ美術は一世紀後半の大月氏の一族「クシャン朝」に入ってから開花する。
紀元130年頃即位したクシャン朝の「カニシカ王」はアショーカ王と並ぶ仏教の保護者で, 「説一切有部」に帰依し、カシミールで500人の聖者に「有部」経典編集の教学を集成する集会(経典結集)を開催したり、馬鳴(めみょう)を連れ帰り敬信したという。
「絹の道」という名は19世紀にドイツの地質学者F.リヒトホーヘンによって付けられた。
前2世紀ころに開かれ、最も古い道はタクマラカン砂漠の南路と中央路で経由地である、安息,大月氏,康居(こうきょ),新疆ウイグル自治区と西域地区を結び、遠くローマまで続く。
仏教は、やがてガンダーラから、このシルクロードを通って東進することになる。
菩薩の成立
大乗仏教の成立には菩薩の出現が重要な契機になっている。
前一、二世紀頃に「ジェータカ」(釈迦の前生物語)を作ったインドの仏教徒により「菩薩」(ボーディ・サットバ)という語が作られた。
仏陀が仏になる前の未だ悟りを得ていない修行時代の段階、あるいは誕生以前の仏陀を表わす場合に「菩薩」という名称が用いられた。
その根底に「悟りを得ることが確定している生ける者」という意味を含み、仏になることを約束された仏陀を表わすのに「菩薩」の語を用いるようになったのが最初であった。
インドの気候は極端で、雨季と乾季の自然の循環がダイナミックに展開して四季が永遠にめぐっている。
同じように生きとし生きるものも永遠に生と死を繰り返す。
それとともに苦も永遠に続くというインド的な世界観となって現世を仮の姿としてとらえて「輪廻転生」という思想ができた。
また、度重なる他民族の侵略があり、その苦からも逃げる道を仏塔に集まった人々は探り始めていた。
そこでは仏塔には仏陀のかわりに「法輪」が描かれた。
この法輪図はインドの象徴で国旗にも描かれている。
法(ダルマ)とは宇宙、自然の摂理。輪(チャクラ)とは循環のことである。
これは輪廻転生の世界観そのものであった。
人々は、法輪を描くことで、いつしか仏陀がこの世の輪を回すものとして崇めたのだろう。
仏陀を慕い、仏舎利が納められた仏塔への信奉者達は、仏塔に供物を捧げて威神力を持った仏陀が現在することを祈った。
仏陀の人格的不滅を信じ続けていたのである。
しかし、仏陀の教義は「この世に自分も含めて絶対なものはない」とした考えに対し、絶対の救済者としての仏陀を求める民衆があり、これを解決しなければ仏教が救済宗教として生れることはできなかった。
「空」の発見
この絶対矛盾を解く鍵を見つけた哲人がいた。それが「空」という概念である。
空(sunya)は否定の表現と同時に相対の否定により肯定となり、そこに絶対を直観することを意図している。
これは教理を臨機応変、自在に創りだせることになり、仏像や菩薩像の出現もまた同様となる。
仏塔の礼拝者に向かって菩薩の自覚を起こした哲人達が仏陀にかわってこの教理を説いた。
この「空」の観念の発見が大乗仏教の成起となったのである。
「有部」のような部派仏教では菩薩という名を釈迦のみに使ったのに対し、大乗仏教ではその観念が変化する。
菩薩は仏陀を信奉し修行を実践しようとする求道者一般の呼称として広く用いるようになっていく。
これも「空」の観念をして可能にしていくのである。
大乗の菩薩の成立が大乗の経典の起こる以前にあった。
求道者としての菩薩の実践の指針として大衆の救済する宗教の意義を確立するための大乗の運動がおこり、一斉に大乗経典が多数作られていったものと思われる。
それは初期の般若経が成立する前に、後述する様々な断片的大乗経典が存在したことからの推測である。
その初期の「般若経」では、菩薩になる段階として、初発心菩薩,行六波羅密菩薩,不退菩薩,一生補処菩薩の四種の菩薩像が最初に説かれた。
次に「華厳経」ができると、菩薩行を十種の段階に分け「十地」として説かれ、後代の「菩薩瓔珞本業経」では、さらに五十二位という階位が整えられた。
そして保つべき戒が示され菩薩行に努めるものは男女にかかわらず成仏しうることを確証するものとした。
大乗仏教ではこのような求道者一般としての菩薩のほかに、理想像としての特定の菩薩がつくられた。
これらの菩薩はすべての生ける者を救うため、いろいろな姿でこの世に現れ、自らは仏になることなく、利他救済にのみ努める、いわば仏に匹敵する最高の理想的菩薩として描かれた。
それゆえ、仏と並んで信仰の対象になってゆくのである。
弥勒菩薩-釈迦の入滅後56億7千万年後にこの世に現れ次の仏陀になると伝えられる菩薩。「将来仏」「当来仏」ともいわれる。
観世音菩薩-法華経より現世利益思想を代表する菩薩として登場。阿弥陀三尊のひとつ。やがて密教的変化から千手観音、馬頭観音など七観音が生れ、後に三十三観音にまで発展する。
文殊菩薩-華厳経に釈迦入滅後生まれ、般若波羅密を説き「般若経」を編集したという。仏陀の左脇に侍し智慧を司る。獅子に乗る姿を常とするが一定ではない。
普賢菩薩-釈迦の実践的理性を司る菩薩。文殊菩薩と並んで釈迦仏の右に脇侍。密教では金剛薩?と同体とされる。
大勢至菩薩-阿弥陀三尊の一つ。阿弥陀仏の右の脇侍菩薩で智慧の光で衆生に菩薩心の種子を与えるとされる。
地蔵菩薩-地獄の入口で衆生を救済するところから村境の道端に祭る境の神の信仰となり子供の霊と結びつき子供の守護神や安産など広く信仰されてゆく。
大乗仏教の成立(マハーヤーナ Mahayana )
従来の仏教に従って行を積んだが、結局究極的な悟りに至る事ができないと考えた僧達や在家の人達は、新しい道を捜し求め、それを見出したことで出家修行者だけでなく誰でも究極の悟りに至る事ができるとして、旧来の仏教を乗り越えた新しい道である大きい乗り物を意味する「大乗」を名乗る新仏教を成立させていった。
道を悟るといっても凡人には無理なことなので、いっそ、道を悟った人の思想を拝むほうが合理的だと考えた。
時あたかもガンダーラで仏像が造られた時期とも重なり、仏像を拝むということが大乗仏教の要素として取り入れられ、そこに衆生の救済という要求が満たされることになったのである。
「大乗仏教」側からは、従来の仏教を「小乗仏教」と呼んだ。
大乗仏教の大きな特質は、前一世紀頃から紀元七世紀頃までに大乗経典が次々に数多く現れ、しかも経典内の増広も見られることである。
小乗経典では釈迦の言葉の集大成であって後世新たな経典が現れるということはないし、増広もありえない。
永遠に創られざる神の意思であるキリスト教の聖書やイスラム教のコーランにもそういうことはありえない。
従って大乗経典は釈迦の説教を後で編纂したものではなく、後代の人々によって書かれたものである。
これは、「誰であろうと自ら正覚して説いた説が仏説として成立しているならば、それを説くものは皆仏陀である」(大乗荘厳経論、270年頃)という論点で成り立つとしている。
このような考えに立つならば、自説も仏説として表現できることになる。
これは覚者とする仏陀が多数存在していくことを意味し、大乗仏教の多仏思想はここにその根拠を見出すことができる。
(仏陀-原義は覚者、悟れる者の意。釈迦も自ら悟ったので仏陀という)
こうして、まず、前一世紀から紀元一世紀にかけて大乗仏教の根本経典である初期の「般若経」が成立する。
般若とはprajna(智慧)の音写で、経典の説く内容は求道者(菩薩)の実践である。
以後、菩薩は観念化し、人を救うための存在、機能となる。
菩薩とは、もともと釈迦が成道して仏陀(覚者)となる以前の求道者であったときの釈迦をさしていたが、大乗仏教において「釈尊」と尊称されるようになる以前の釈迦と同様に、自らも求道の実践を通して成道しようとする強い意思に基づいて修行を積むことにより菩薩(求道者)になれる。
それを大乗の根本理念として「般若経」ができた。
この般若経典は後からつくり出されてゆく多くの大乗経典の思想的根拠になっていく。
そこには出家者だけでなく在家にあってそれを可能にすると説いた所に「大きい乗り物」である大乗仏教としての立場があった。
インド人が「ゼロ」を発見した。仏教はこれに哲学的要素の「空」の世界を重ねた。
大乗仏教の根本として「般若経」が最初の経典として一世紀頃つくられ、十世紀に至る長い年月の間に多くの大乗仏教経典が成立し、多くの哲学的天才が菩薩(求道者)として現れてくる。
それに伴って、二世紀の「龍樹菩薩」の出現の前に、『般若経』の他に『法華経』『華厳経』『維摩経』など第一期の大乗経典が著されていったのである。
- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)
a:5238 t:3 y:3