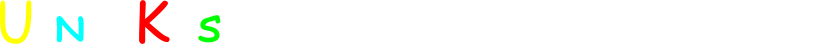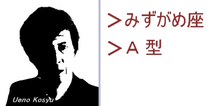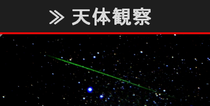12桜の季節
いけばな歳時記 季節の節目に出会う花!
巡りくる桜の季節
2012年4月25日(水) spectator:4333
- 新潟市 護国神社参道

- 信濃川やすらぎ堤にて
今年の新潟の桜は寒さが続き開花が遅かった。
今日25日市内の桜の撮影に行ってきた。まさに春蘭漫。雪柳やチューリップも満開だ!
うららかな春の半日を存分に楽しんだ。
今年は古事記が編纂されてからちょうど千三百年の年にあたる。
我国に現存する最古の文献である古事記の上巻(かみつまき)の天孫降臨のくだりにすでに桜が登場する。
高天原(天上の世界)を支配するアマテラスは葦原中国(地上の世界)を治めるべく孫のホノニニギノ命を使わした。
これが天孫降臨である。
そこでホノニニギノ命は美しいコノハナノサクヤ姫(木花之佐久夜毘売)と結婚する。
- 新潟市 旧税関
このコノハナノサクヤ姫が桜の意味を示しているのだという。
文中には桜という文字は出てこない。
初見するのは下巻(しもつまき)の履中天皇の宮殿の名前が「伊波礼の若桜の宮」のそれである。
国語辞典では「木の花」は桜花の異称。「此の花」は梅花の雅称としているように、
- 新潟市 西大畑公園
コノハナノサクヤ姫は桜を表しているというのが定説となっている。
サクヤのヤは感動を意味する助詞で、木の花が美しく咲いているという感動を美しい乙女に重ねた名前でその花は桜でなければならないという推測である。
桜は古には佐久良、佐区羅、佐具良などと書かれ、その語源も麗らかに咲くから咲麗(さくうら)からさくらになったなど諸説あってはっきりしていない。
サは田の神、クラは座を意味し、田の神の座からきているという説がある。
田植えに関する言葉には、早苗、早乙女、五月などがあり、そこから田の神と結びつくのが「サ」の意味だとすればわかりやすい。
サクラは「田の神が依り付く樹」として名前が付いたことになる。
京都の今宮神社に古から続く宮廷の鎮花祭の遺風を残す「やすらい祭」がある。
- 新潟市 護国神社
陰暦の三月十日の神事で、新暦では四月十日前後になる。
当然その対象の花は桜である。
そのなかで桜に対して「やすらえ花や」という呪言が唱えられる。
これは、花の散り急ぐのを鎮めてくださいという祈りとして使われている。
なぜか。
日本民族は農耕民族で秋の稲の豊凶は重大な関心事であった。
桜の開花を合図に農作業が始る。その春の桜花を秋の稲穂の花に見立てて、花の散るのをどうか遅くなりますようにと願った。
そこでは古くは「ためらう」という意味だった「やすらえ」という言葉が使われていた。
稲の花が咲くころはちょうど台風のシーズンにあたり、開花が阻害されると不作に結びつく。
農作業の始りを告げる桜の花が散り急ぐことへの恐れが秋への豊作を願う神事となったのが鎮花祭のはじまりであったのである。
当時の桜を観る人々は真剣に祈ったことだろう。
その感情は現在の「お花見」のような楽しみとか優雅さなどとは無縁であった。
それがやがて稲を害虫から守ることへの祈りにもなり、転じて人の厄病を払うという意味に拡散していったのである。
では、ホノニニギノ命とコノハナノサクヤ姫の結婚にはどのような意味が込められていたのだろうか。
天孫のホノニニギノ命は、穂のにぎにぎしく(豊かに)実るという意味で、稲の精霊を象徴するという。
天下ったところが高千穂の峰だが、これは特定の山ではなく、本来、高くたくさん(千)積み上げた稲穂のことをいう。
古代の宗教行事に山積みした稲の上に稲の神が降臨するという神事があり、それが天孫降臨という物語となって伝承された。
稲の精霊であるホノニニギノ命と、コノハナノサクヤ姫がサクラを擬人化した名前ならその結びつきは素直に理解ができるのではないか。
春、サクラが麗しく咲き続ける様子とそれに豊作を託した稲の精霊が結びついていったのはごく当然のこととなる。
桜の咲き具合を見て稲作の豊凶を観ていた古代人の感情が現代の我々のなかには残っている。
春蘭漫と咲く桜の花を愛でる気持ちと同時に散る花にも風情を感じる心が日本人の心情のなかに深く沈澱していったのである。
木花之佐久夜毘売とはどんな女性だったのだろうか。
日本の象徴となった桜の花に託された先人の思いを想像しながら今年も春本番の桜たちを見に行ってこよう。
- 桜吹雪 ■我家の庭に咲く桜と椿
- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)
a:4333 t:5 y:8