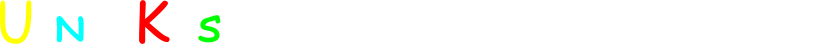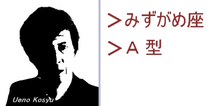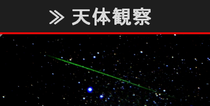重陽祭10
いけばな歳時記 季節の節目に出会う花!
重陽の節句
2010年10月16日(土) spectator:5223
- 弥彦神社の菊祭
今日は旧暦の9月9日。奇数の最も大きい数字の9が重なる日、五節句のうちの五番目の「重陽の節句」である。
菊の節句といわれるこの行事も新暦では菊の咲く季節と合わなくなり、明治以後は印象が薄くなった。
中国でこの重陽の節句が正式に認められたのは漢代で、『西京雑記』によると、漢の高祖の愛妾が殺害された後、宮廷より放逐されたその侍女が、9月9日は宮廷では茱萸(しゅゆ)を肘に下げ、菊酒を飲み長寿を祈る習慣があったと人々に話したことから、民間でも祝われるようになったとされている。
茱萸は芳香のある植物で、菊とともに邪気を払うという共通点がある。五節句には邪気を払ったり、健康を願う芳香のある植物との関係が深い。
茱萸は原産が中国や韓国で、山茱萸(さんしゅゆ)の名で日本に渡来した。
香りが高く名前が似ていることから、山椒(さんしょ)や、実が似ていることからグミと混同されるが、
早春に黄金色の花をびっしりつける様子から、「春黄金(はるこがね)」、また秋には赤い実をたくさん付けるので「秋茜(あきあかね)」の別名がある。
現在でも黄色の花をつける山茱萸は春の「いけばな」の花材である。
菊は日本では奈良時代ころから宮中や寺院で菊を観賞することが行われていたが、平安時代になると中国思想の影響を受け「重陽の節会(ちょうようのせちえ)」として宮中の正式行事となり、天皇や貴族が紫宸殿で詩を詠んだり菊の花を浸した菊花酒を飲み、茱萸(しゅゆ)を掛けてけがれを祓い長寿を願う菊花の宴が催されるようになった。
菊の花は「翁草〔おきなくさ〕」「千代見草〔ちよみくさ〕」「齢草〔よわいくさ〕」とも呼ばれ、古来中国では邪気を祓う不老長寿の薬とされていた。
それにあやかるように菊の被綿(きせわた)といって、9月9日の前夜にまだ蕾の菊の花に綿をかぶせて菊の香りと夜露をしみこませ、その綿で身体を拭き清める。それは枕草子や紫式部日記のなかにも書かれている。
また、このころから菊に関する歌合せや、「菊合わせ」といった現代にも続く菊の品評会が盛んに行われるようになった。
そして、重陽の節句はいつからともなく「菊の節句」とも呼ばれるようになる。
その菊が日本を代表する花として天皇家の紋章となった。花びらの数は十六枚である。
嵯峨天皇の御紋は裏菊十六紋といって、菊を裏から見たデザインといわれている。とてもモダンなセンスが感じられる。
十六という数字は天の数が7、地の数が9とされていて、天と地の数を合わせた数字が16となり恐れ多いということで一般の菊の紋章には十六紋は使われない。
3月3日、5月5日、7月7日のように奇数を重ねて節会としているのは中国の陰陽思想からきている。
陰と陽とはもともとは天候と関係する言葉で、陰は曇りや日影、陽は日差しや日向の意味として『詩経』などの古書に表れる。
そこから、すべての事象には光と影、生と死など相反する二つの要素が同時に存在し、陰と陽は一体の現象であるとして森羅万象、宇宙のありとあらゆる物は、陰と陽の二気によって消長盛衰し、その二気が調和して初めて自然の秩序が保たれるという説である。
ここから生まれた迷信も多いのだが、数字も陰の数は偶数。陽の数は奇数とされた。
偶数は割り切れるので武士(もののふ)の社会では兜が割れることにつながり、死の数とされ、奇数は割り切れないことから死に対して生きる意味で活の数となる。
今でも料理の盛付には5品、7品と奇数が使われる。偶数が嫌われるのはこのことが日本人のDNAに染み込んでいるからなのだろう。
そこで、生きること、繁栄する意味となる奇数の重なる日を節会として祝う「五節句」が嵯峨天皇の時代に制定された。
この節度ある暮らしがこれまでの日本人の気質を形作ってきたともいえる。
その最後を飾る最も大きい陽の数、9が重なる「重陽の節句」は秋の終りの収穫祭であり、寒い冬を迎えるにあたり命が芽吹く春までの健康を祈る祭りでもあった。
ちょうどこの時期に芳香を放ち邪気を払うという菊の存在があった。江戸時代には菊作りは男性の教養とまで言われるほど盛んになっていった。
しかし、新暦の9月9日ではまだ菊も蕾でしかなく旧暦の今日でなくてはこの節句は成り立たなかったのである。
今日ではその菊も、人工的に季節を調節して年中出回っているが、やはり秋を代表する花と云えば菊ということになるだろう。
江戸時代まで庶民の間でも盛んだったこの「重陽の節句」は、現在では宮中や一部の神社でしか行われなくなったが、各地に残る「菊祭り」となってそのにぎわいを今に伝えている。
- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)
a:5223 t:1 y:0