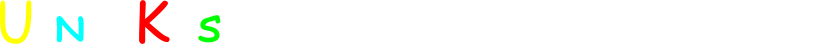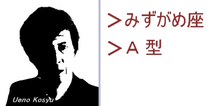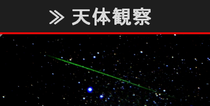桐蔭軒無言録
■ 桐蔭軒無言録 (私本太平記にみる足利尊氏の初七日の論評)
2013年1月7日(月)
- 等持院-足利尊氏の墓所
いけばな嵯峨御流の総司所が京都大覚寺にあり、大覚寺統と呼ばれた南朝の御所であったことから、南北朝時代のことをもっと詳しく知りたくて、吉川英治の「私本太平記」を読む。
全八巻におよぶ大作で、その最後に載せられていたのが「桐蔭軒無言録」である。
この終章の「黒白問答」が「私本太平記」の主題であったことは疑う余地がない。
数十年の大乱を経て、室町幕府を興した足利尊氏が薨じて八日目、都中で法要が続く中、西洞院綾小路の職屋敷に二千人もの盲人が諸国から集まり、故人尊氏の遺徳に報う琵琶法要が行われた。
この記録は、その折に、盲人たちと覚一法師が、尊氏の功罪の是々非々だの、疑惑視する世評に対する質疑応答を口授したものである。
この日の施主、検校覚一も盲人である。
明石の検校とも呼ばれていた覚一法師は、当道派の主座で、足利尊氏の従兄弟にあたる。
二十歳ころより琵琶の名人の聞こえがあり、何度も宮中にも召されていた。
晩年、当道の如一に就いて、琵琶の奥義を窮めた人物である。
覚一検校の足利将軍家への献策により、ひとつの盲人組織と、盲人を総括する職屋敷の土地がここに与えられていた。
そこでは従来乞食扱いされていた盲の琵琶弾きを収容して、これに官の印可と保護を与え、すさんだ大道芸に平曲のよさを習得させ、筋のいい者に座の職階を上げて、座頭、勾当などの名誉をさずける「座」を形成していた。
琵琶が弾けない者には、鍼、灸冶、按摩、売卜の道を教え、職屋敷の制度下で何らかの生業と保護が与えられ、冥加金や印可料を職屋敷の座に納めていた。
盲官には、検校、別当、勾当、座頭の職位のほか、幾十階もの階級があった。
検校は盲最上の位であり、緋の衣に検校帽子をかぶり、後ろに燕尾を垂れ、唐画をみるような身なりであった。
〔 大和の結崎の田楽能の一座があり、大和の仏会神事の催しにも預かり、能舞の一流を打ち創てる途中にあった。その立役者が千早篭城のなかで生まれ、幼名を観世丸と言った大和結崎座の観世清次(当時25歳)である。この日、同室している。〕
吉川英治は、正本が正しく伝えられるはずがないとし、後世には増項もあり得るとしているが、尊氏が亡くなった時点での問答は、時代の空気を生々しく描きだす。
私本太平記に【抜抄】し掲載したものをそのまま記す。
質問者は当夜の盲人三、四十名で、答えるのは覚一検校である。
問「まず、序問の僭越をお許しください。何事も腹蔵なく問え腹蔵なく答えん、との仰せですが」
答「そのとおりです」
問「けれどそれが過ぎて、御生前の批評やら世上の悪声などに及んだら、先将軍(尊氏)の霊に対し奉って、失礼にはあたりませぬか」
答「あたりません」
問「でも、主旨の御供養にはなりますまいが」
答「いや、何よりの大供養なりと信じます。棺を蔽って定まるとか。
生きとし生きる者のほんとの声を、尊氏さまも今は千万部のお経よりは、泉下で聞きたいとしておられるものと存じまする。
問「はて、いかにとは申せ、検校どのには、先将軍のお心をそこまで、御断言できますか」
答「幼少より存じあげ、かたがた、薨去の当夜まで、お枕べに近い控えの間にいて、夢寐のまもなきおくるしみや折々のおん譫言さえ洩れ伺うておりました。いささか御胸中を拝知しておる一人かと自負しております」
問「死ぬるまぎわまでおん悩みとしていた第一のことは何でしたろうか」
答「たくさんな人間をこの地上で殺したことでしょう」
問「尊氏公が殺したわけでもないでしょうに」
答「あのお方の正直さではそう逃げられぬ。でも家を興すには戦争もせねばならん、戦争へのぞむからは勝つため敵も殺さねばならん、が末始終には、これは天下の諸民を助けることになるのだ、世を安きに建て直す途上では仕方がないと、一生わき目もふらぬおすがただったものでしょう」
問「それがいつ頃からお心の悩みと変わったものですか」
答「私にもわかりません。おそらくは曲がりなりにも幕府が出来たころでしょうか」
衆声「……解せぬことのう?」
問「幕府の御成立は、尊氏公にすれば、大望成就、得意でありましょうに、なぜそれを境に、お迷いが始まったので」
答「たとえば粘土を以て一つの円い陶壷を仕上げようとなされていたものが、真二つとなってしまったからでした」
問「朝廷の両立ならば、その亀裂は昔からの古傷で、いま始まったことではない」
答「いや、何よりは足利自体の内訌です。股肱の臣と臣とが啀みあい、骨肉の弟御や異母子までが、みな主体に叛いてわが身をわが歯で啖いはじめました。
問「世間の蔭口では、それも尊氏公が政略のやり損じで、御自分の嘘から御自分を破ったものと申しますが」
答「さよう。私もそんな気がする。一例をあげれば、清水寺の願文など、あれを書かれた御本心が疑われてならないのです。
―この世の幸はみな弟直義に与え給え、この尊氏にはただ後生のみを授け給われ―と、ひたすら遁世の念と弟思いが溢れているあの願文なのですから」
問「それが、その弟御をついには毒殺なさるとは」
答「げに、人の心とは怪しいものです。とはいえ、清水寺の願文が嘘の文字とは申せませぬ。
あれを書いたときのお心はその通りな尊氏さまであったに相違ございませぬゆえ」
問「不しつけに申すなれば、先将軍というお方は、何せい、われらどもには解らぬことだらけですが」
答「げに、矛盾にみちたお方でした。情にもろく、情のお人かと思えば人以上に冷たい。藤夜叉という女性へも、直冬どのにも、あの冷たさは異常です。
そして閨房とて、ほかに入れた女性もありません。
すべてを大望にかけて御自分をころし切っていたものでありましょうが」
問「でも、その大望も、御自身ついに滅失されたのでは」
答「いや、さいごには、その滅失を取り戻そうとなされた焦燥が、直義さまを、あんな思いきった御処置になされた、第一の御理由であったように思われまする」
問「検校。てまえにも一つ借問させていただきます。
―夢想国師は、尊氏公の長所三つを賞めて、一は生死を超脱している、二には慈悲心ふかく人の非もよく宥す、三には無欲恬淡で物に慳貪の風がない―と。その通りでございましょうか」
答「御長所ならば、もっとありましょう。尊氏さまの周りには、つねに大どかな和がありました。
ほがらかで茫洋で、小さい事にはこだわらず、お気楽で威張ったところが少しもない」
問「ではずいぶん人好きのするお人柄としか思いませぬが」
答「そうです。たとえば八朔の朝など、諸家の進物で広間が埋まるほどな物も、そばから人に与えてしまうので、夕には一物もなかったということです。
ですから土地なども奪るにしたがって武士どもに分け与え、御自身は権力すらも実はそんなに欲しがっておられな かったと思われまする」
問「だのになぜ一面では、権謀術策、無常苛烈、血も涙もない政略家のように誤られたのでございましょうか」
答「いや、それも誤りではありません。悪と善、鬼と仏、相反する二つのものを一体のうちに交錯して持つふしぎな御仁」
問「すこし分かってまいりました。後醍醐天皇とのお争いなどもそれでしょうな」
答「これまでの歴代にも現れなかった烈しい御気性の天皇と、めったにこの国の人傑にも出ぬようなお人とが、同時代に出て、しかも相反する理想をどちらも押し通そうとなされたもの。宿命の大乱と申すしかありませぬ」
問「その大乱というのが、てまえども庶民、わけて盲人の身には、何のためにやってござるやら、武家衆や公家衆の、正気のほどが解りませんが」
答「たれにも解ることではございますまい。
もし足利殿なかったら、戦争は起らなかったか。後醍醐のきみが武家に取って代わる御謀反気を持たれなかったら、かような乱世にはならなかったか。そんな単純には言い解けませぬし」
問「では誰が、いや何が、こんな凄まじい世にしたのでしょうか」
答「下手人はないのですよ」
衆声「ほう?ないとは」
答「しいてあるといえばあるともいえましょう。一部の陰謀や火ツケで出来るものではありません。全土に素地ができているから始まったことなのです。
源平、鎌倉、北条と長い世々を経てここまで来たこの国の政治、経済、宗教、地方の事情、庶民の生業、武家のあり方、朝廷のお考え―までをふくんだ歴史の行きづまりというものが、どうしてもいちど火を噴いて、社会の容をあらためなければ、二ッ進もさっちも動きがとれない、そして次の新しい世代も迎えることができない、いわば国の進歩に伴う苦悶が何より因かと思われまする」
問「では、何十万の死者も、その犠牲というわけですか」
答「北条殿、新田殿、足利殿、そして後醍醐のきみも、正成どのも、犠牲であるに変わりはない」
問「ほかに工夫はないものでしょうか。そんな殺し合いをしないでもすむ―」
答「それが智恵です。けれど人間はまだ悲しいかな、そこまで叡智の持ち主ではありませぬ」
衆の声「はアて?どうじゃ同朋たち。検校どのの今のおはなし。合点がゆくか」
衆「いや合点なまいらぬ。大乱の因は地震のようなもので、火ツケの悪徒のせいではない。ただ、人間全体が叡智にさえなれば、戦はなくてすむという仰せだが」
答「ま、同座の衆、お静かに。今の言い方では宇宙から下界を見たような感をうけたかもしれぬが」
衆「その通りじゃ。こんな馬鹿な戦を果てなくやっていられたら、人間全部が一生の五、六十年はまるつぶれになってしもう」
答「ならば旧態のままでよいか。それも不断に進む世の自然に反します。行き詰まりの世が腐りだすと、腐り放題に腐えてゆく。いやでもまたその無秩序や不平が恐ろしい不安を醸して来ますのでな」
問「と仰っしゃるのは庶民も戦争の手伝い人だと仰っしゃるので」
答「庶民は戦争にふるふるです。ですが時には、事を好む野次馬性と射幸心にもうごかされやすい」
問「なるほど、そんな浮浪もいるにはいますな。けれど戦争の元凶は、やはり権力の中に住む人間どもにありとしか思われぬ」
答「……権力。そうです。権力欲とは何なのか。摩訶不思議な魅力をもって人間どもを操り世を動かす恐ろしいものに相違ございません」
問「天皇、女院、将軍、執事、大名、大名の下の武士、みな権力に憑かれて、それが戦争の」
答「ああいや、他を言って自分を措いてはいけません。それは私たち盲人の中にさえあるものだ。この座のうちにも潜んでいるものです。
恐い。何がといって、権力の魅力ほど恐いものはない。
下手人はこれと見つけたり!としておきましょう」
問「では話をかえて。―当今の武士の廃れは嘆かわしい。裏切り、偽セ降参などは朝飯前。これを源平時代の武士にくらべると、雲泥のちがいですが」
答「堕落も泥ンこも、次へたどりつく途中と思えば」
問「ではまだ当分続くのでしょうか、こんならちゃくちゃのない風潮と、暗黒時代が」
答「が、必ず朝は来ます。朝の来ない夜はない」
問「何か、曙の兆しが、ちょっとでも何処かに見えていましょうか」
答「それはある、萌えかけている」
問「どこにです」
答「地の下、つまり庶民の中にです。長い戦乱は、みなを苦しめたには違いないが、庶民の生活はいつともなくずんと肥えていましょうが。
外へこぼれ出た宮廷の文化。分散された武家の財力、それらも吸って」
問「そういえば、虐げられつつ、庶民の生活は枯草のように、前より根強くなり進んで来ておりますな」
答「自分の力に自覚を持って来たからです。田楽能一つに見ても、以前は権門の物でしたが、当今では、河原小屋や辻能で、庶民に愛され、庶民が育てているものとなっている」
衆「いかにも、いかにも」
答「また、われら盲人にしても、このような職屋敷を持ち、以前にはなかった職能と人なみの生活を得たのは、やはり暗黒の世の陣痛が生んでくれた一つの光明であったのではないでしょうか」
問「光明……今の世にも光明があるとは初めて伺いました……。無限の暗黒、無限の合戦、無限の南北両朝のお争いかと悲しまれておりましたが」
答「長い時の流れからみれば、わたくしどもが見た半生の巷など一瞬のまに過ぎませぬ。大地とはそれ自体、刻々と易って行く生き物ですから、易るなといっても易らずにおりません。そして易り易ってゆく地上には、時にしたがって時代の使命を担った新しい人物が出現して来る」
問「そして次の時代を耕すというわけですか」
答「そうです。それが血で耕されるような季節こそ人間最大な不幸の時期に当たりましょう。
思えば北条殿、新田殿、足利殿、また後醍醐のきみや、幾多の連枝、廷臣もみなこの時に生まれ合せて、いやでも超えねばならぬ悪時代をこえるために戦ったものとも申せましょうか。……と私は考えるのです。
そう思い去り思い来ると、何十万の白骨もくるめて、上下なく、誰も彼も、ただあわれでなりません。
……このあわれを誰よりもよく知って、人間の叡智を持てと、あえてすべてを祈り捧げて壮烈な自滅を取ったようなお方もただ一人はありました」
問「それはどなたです」
答「正成どのです」
衆「……ああ、げにも」
問「しかし、それでは運命とは何と不公平なものでしょう。
楠木殿のようなお方もある一方、佐々木道誉どののような世渡り上手で狡いお人が、憎ていにいよいよ栄えておりましょうがな。
やはり正直者はばかをみるということですかな」
答「さよう一概にはいえませぬ。道誉どのの無節操や婆娑羅ぶりも、部門の風潮で、あのお方一個が狡くて驕慢なわけでもない。
むしろ憚りなく、生きたい生き方をやって退けるなどは、それも一流の正直で独自な頭の良さともいえましょうか」
問「ほ、これは意外な御賞揚ではある」
答「いや賞めはしません。ただ宇宙は人間それぞれの性をよく公平に“時の役割”に使っていると言いたいのです。
彼が道楽に創めた立花(生け花)、闘茶(茶道)なども、やがて観世清次どのの舞能のごとく、案外、ゆくすえ世の文化に大きく開花を見るやもしれません。
なべて人に役立つものは亡びない。けれどどんな英傑の夢も武力の業はあとかたもなくなる。ですから、もののふとは、あわれなのです。
とくに尊氏さまの御一生などは、無残極まるものでしかない」
問「が、お名は千載に残る」
答「いや、それも覇力の名ですから時の移ろい次第です。
ひとたび足利氏が衰えれば、逆賊、佞将、涙なき権謀の人物と、あらゆる悪名や人の唾を浴びるときがないとも限りませぬ。
……ですがわが仁山大居士はもう御観念でしょう。
何事も大悟して、世の流れのままにどんな毀誉褒貶もあの薄らあばたを幻として地下に笑っておいであるに相違ございませぬ」
と問答記事はここで終わっている。
桐蔭軒とは琵琶道場のわきに大きな桐の木があったことからの名である。
この「黒白問答」に続いて、仁山大居士琵琶法要、観世清次の手向けの能があったことが記されている。
足利幕府の基盤も未だ脆弱で、安定するのに三代将軍義満の時代まで待たなくてはならなかったのだが、尊氏が亡くなったという時点での、時代の意味、争いの本質、戦乱に明け暮れする時代の人となりを冷静に分析し、未来における尊氏像まで予見し、さらに将来の日本文化にまで思いを致していることに、眼が開かれるようで、驚嘆の思いを禁じえない。
足利尊氏という生の人間像と、南北朝時代の空気をいきいきと写したこの記録は、盲人たちの視点という特異性で異彩を放っており、歴史の必然の中に残されてきた一級の資料であることは間違いないだろう。
この動乱の時代に、このような考えができる高度な知性があったればこそ、日本という国が文化国家としての地位を21世紀においても世界に示しうる、その原資をここにも見るのである。
また、現代にも続く日本文化の黎明がここにあり、百十年後の足利義政の時代の応仁の乱では、日本文化の源流として大きく花開くことを思うと、日本の優れた文化の起こりは、戦争と対極のところで醸成されてきたものであり、単純に美を競うものではなく、精神的な拠り所として磨き上げられてきたことが理解できるのではないだろうか。
- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)
a:4496 t:1 y:0