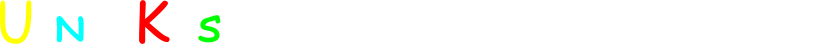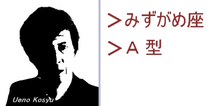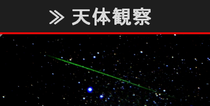プロフィール2
上野 恒洲 プロフィール 2
いけばなとの出会い(記憶に残る経験)
いけばなの稽古中だったかと思うが、忘れられない出来事がある。
一本の藪椿の枝が花瓶に挿してあった。

花が一輪だけ7分咲き位に咲いていた。
その何とも言えない美しさに自然と引き寄せられるように顔を近づける。
「きれいだね~」思わず心の底から何度も繰り返し話しかけていた。
一点の汚れもないビロードのように輝く深紅のその色は今まで見たこともない艶やかさに満ちていた。
それから数日の間に、その椿の木の蕾も次々に咲いてはポトリ、ポトリと落ちていく。
やがて花もすべて終わろうとしている頃、一輪だけ茶色になっても落ちずにいる花にふと目がいった。
衝撃が走った!
近づいて確かめる。間違いなくあの最初に声をかけた花だった。その瞬間、初めて花と心が通えあえたような嬉しさがこみあげてきた。
あのときの一輪の椿の花の愛おしさ、けなげさは、今なお忘れることができない。
これ以上の白い色はないだろうと思うくらいに白い花がある。その厳しい環境に適応して咲く高山植物に出会うため、山に行くようになったのもこの頃からだったかと思う。
もともと臆病で、深く険しい高い山などに行く勇気などなかったのだが、それを助けてくれたのは妻の美砂子だった。北岳から槍ケ岳や穂高、近郊の山まで、ほとんどの山は夫婦で登っている。
40代からの十数年間は、最多の年で、年に25回くらい、山登りに熱中した。
そこで見た景色、高山植物、野生動物など、いつしか大自然のとりこになっていた。自然の持つ多様性、神秘的現象、厳しい環境に生きる動植物たち。これらの四季のみごとな営みは膨大な量の写真、ビデオに収めてきた。
自然は季節ごと見事に住み分けをして、無駄なものはいっさい残さない。その知恵と潔さ、簡潔さに魅了され続けてきたのである。
もうひとつ、忘れられない光景がある。
テレビのニュースで,ある彗星(百武彗星)が話題になった時、写真に撮ってみたくて400mm望遠レンズを持ち出し撮ったところ、かなりよく撮れていたことから星の写真撮影にも熱中した。
五大惑星が西の空に一直線になるという現象が起きた。その過程で金星と火星と土星が正三角形になる日があり、これはキリストが生まれた年にも起こった極めて稀な現象だという。雲の切れ間を探し県境に近い笹川流れまで走って、ようやく撮影に成功した。
フイルムも使い果たし、帰路、海岸線を走っていると後方から何か強い気配を感じ、車を止めて振り返った。三角形の下の頂点にあるひときわ明るい金星が水平線に近づいていた。
そのマイナス4等星になった金星の光が驚くほどの光の束となって太陽のそれのように海上を照らし出していたのである。
暗黒の空と海に金星からの一条の光線だけが私に向かって伸びていた…。その初めて観る光景に圧倒され、光が水平線に吸込まれるようにして消えてゆくまで立ち尽くしたのだった。
空海が確か室戸岬の洞窟で修行中、金星が口に飛び込み修行を成就したという話を思い出した。
- いけばなとの出会い
20代は社会に出てから十年ほど建設会社で学校などの公共施設や各種の商業施設を造っていた。高度成長期の右肩上がりの時代である。自分が線を引いた図面により、多くの職種によって建物が造りだされてゆく。それを管理しながら完成させてゆくことは快感であった。
しかし、30代半ばから苦悩が始まった。利害関係や競争原理、漠然とした未来への深い不安、何かが違って見えだしていた。
それを救ってくれたのが「いけばな」だった。
いけばな教室で教えるかたわら、京都の嵯峨御流総司所に春と秋の一週間の短期研修、やがて毎月一回通うようになり7年間をそこで学んだ。
私の母、上野美甫が新潟に新潟嵯峨流会を立ち上げていて、すでに百人以上の師範を育てていた。
幼いころからそういう環境にあったので師範の免状は二十代のころ取得していたが、京都に通う間に正教授、特別階級、そして称号を得た。
そして、母の病気がきっかけで、司所長を引き継ぐ形になった。
こうして、21世紀の今日までいけばなに携わるうち、自然の神秘にふれ、たくさんの感動と教訓を得たことは大きな心の財産となった。
科学の発達は決して人々を幸福にはしないということも2世紀にわたる壮大な実験で実証された。
物事の本質にはプラス面とマイナス面、表裏一体の関係が必ず存在する。
先人はモノの豊かさより精神の充実の方を重んじ、また、自然と乖離する生活を戒めるために道具の寸法なども宇宙の法則の数字をもとにしてモノづくりをしていたのである。
これまで、いけばなを通じて人間と自然の関係についても多くのことを学ばせていただいた。
伝統とは、その時代を代表する価値観を磨き上げてきたものである。
いけばなをはじめ長年にわたり磨かれてきた日本の伝統文化は、日本の自然風土のなかで自己実現する道としてその時代の価値観を止揚してこそ今日まで発展してきた。
その意味で伝統文化を学ぶということは、かけがえのない自然から、そして先人の修練された研鑽のなかから未来への生きるためのエネルギーを形にしていくヒントにつながると信ずるからである。
いま、このすばらしい日本の文化を、いけばな を通じて世界に紹介することに引き続き取り組んでゆきたいと覚悟を新たにしているところである。

a:4149 t:1 y:1