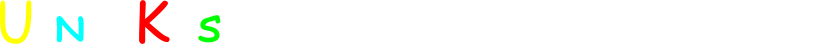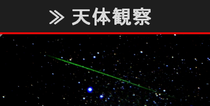いけばなの美学-2
■ いけばなの美学-2 (いけばなの多様な発展を促したもの。)
2010年1月25日(水)
いけばなの造形
江戸時代の立花の盛衰
なぜ、いけばなが立花様式という花を立てることから始まったのか。
それは仏教が導入され供花に使われた花瓶の形状からきていた。
瓶ののどの部分が細く、瓶口がやや広がった縦長の水瓶形(すいびょうがた)の花器で、土拍子口(とひょうしぐち)と呼ばれる中国の花瓶を仏に供えるときの真の花瓶と定めていて、その形状ゆえに自然と直立する花型になった。
そこに日本的な依代という神聖観を重ねて、生ける花材に意味をもたせて花を立てていけたのである。
初期の「たて花」はその大きさも高さ1m足らずだったものが、やがて宗教色が薄められて観賞に供される目的で三具足でいけられたものから、様々な場所でいけられるにつれ、その構成も変化し、大型化していき、中には2mを超える作品もあらわれる。
特殊な例では奈良の東大寺大仏殿の立花は12mもの高さがあったといわれている。
また花の大きさに合わせるように国内産の様々な型の立花専用の花器が生産されるようになった。
馬盥で代用していたものが砂の物といわれる花型専用の大型の花器も作られるなど、いけばなの造形上最も重要な花と花器との造型上の調和が整えられることになってゆく。
立花(たてはな)の最初の構成要素は、「心と下草」といった程度だったのが、座敷飾をはなれ自由に空間を選ぶことにより徐々に役枝が増えてゆき、変化してゆく。
役枝も、心を中心として、前、後、右、左、右下、中、下草と分類するようになり、「専應口伝」(「専應花伝書、又は花伝書」とも云う)では、いろゑ・賞翫(しょうがん)の枝・主居・客居・前面・影向うの枝・見越し・風持(ふうたい)の枝。といった名称がつく。
そして立花(たてはな)は江戸時代初期(17世紀)に、二代目池坊専好(せんこう)によって飛躍的に発展する。
後水尾天皇は年に三十数回もいけばな展を催すほどいけばなに傾倒した天皇で、専好より指導を受けた。
いけばな界のリーダー的存在になった専好の作風は一世を風靡する。
天和三年(1683年)版行の二代目専好の作風を集大成した「立花大全」が著されると、それまでの「たてはな」という呼び方から「りっか」という名称に改められた。
「立花大全」も「りっかたいぜん」と読む。
立花はさらに発展して、各役枝を「七つ道具」として、真(しん)、副(そえ)、副請(そえうけ)、真隠(しんかくし)、見越(みこし)、流枝(ながしえだ)、前置(まえおき)として定め、小道具を「仕舞(しまい)」として、控枝、胴作(どうづくり)、大葉、後囲(うしろかこい)、木留、草留、会釈(えしゃく)などの枝に至るまで多くの要素を、役枝や小枝の寸法や振出方向も明確に決められ、さらに役枝は「九つ道具」とその数を増やしてゆき、型としての規矩が完成してゆくのであった。
指南書である花伝書も次々に版行され、「立花」は江戸の大衆文化のなかに広く受け入れられてゆくことになる。
しかし、その反面、細かく規定された立花(りっか)は、ややもするとその形が鋳型に当てはめたような定型化をしてしまうという危険があった。
完成度を高めるために細かく制限を加えた結果、造形としては自由も発展も規制されてしまうというジレンマに陥り、極端な変形した造形を試みた作風も出たが所詮異端児扱いされるに留まった。
この類型化した「型」の規制による束縛はやがてマンネリとなり、時代のニーズが変化してゆくにつれ、新たな造形としてのいけばなの形が求められてゆくことになってゆく。
風流と粋
風流という意味には、本来聖賢の伝えた遺風から転じて雅(みやび)で風雅ということや、また個性的で趣きのあるという意味にも用いられた。
民俗芸能においては、花を飾って練り歩くための花傘(はながさ)や花で飾った花車も花との関わりの中に見ることができる。
平安時代には花合せなどが派手になってゆき、南北朝時代の「ばさら大名」として有名な破天荒な武将、佐々木道誉は大原野の勝持寺において四本の桜の大木の根の周りに大きな真鍮を鋳型に流し込んで花器を造り、自然のままの桜の木をいけばなにしてしまうというパフォーマンスを演出した。
このような反骨的な趣向なども「風流心」の顕れとみることができる。
こうした趣向をこらすということで本来仏教の供花であった花との関係を継承しつつ、幾世代にわたりいけばなに創造性を積み重ねることで風流のこころも育むこととなった。
したがってその時代の趣向、風流心を求める精神が、前の時代の法式を止揚しつつ創造的発展を遂げて新しい造形美を創り出してきたといえる。
中世の風流心は華麗な美や装飾のなかで「立花」という豪華ないけばなを発展させた。
さらに枯淡風雅な境地から連歌、俳諧、茶の湯といった簡素で自由な世界も同時に求められ、そこから風流とは一味違う「粋」という美意識が江戸に興り、その時代を代表する感性へと変化してゆく。
茶道のことに少し触れておく。
臨済宗の僧「栄西」が持ち帰った「お茶」は禅宗の作法の中で日本的な「茶の湯」になって発展していった。
安土桃山時代に「千利休」によって完成された「侘び茶」は武士の間で隆盛を遂げる。
その茶室の中心となる床の間には「茶花」が飾られる。
利休のころの茶花はその日その茶席、一回限りの花であってまさに一期一会の花であった。
秀吉とのエピソードでは、有名な朝顔の話や、梅の花びらを器に浮かべるなどの多くの有名な逸話が残る。
これらは、規範や型などをもたず創意工夫とアイデアで生み出された独創的な芸術の花であった。
このように茶花は法式を持たない、いわば自由と高い精神性を持っていた。
その本意のなかで「花は野にあるように」として技巧を用いずに自然のあるがままの姿を表現することを重視していた。
「仙伝抄」など最古の花伝書(増稿がみられるが)にも、初めから「規範の花」と「自由な花」が著されていた。
結果的には、いけばなにおいてその規範の花と自由の花が交互に歴史上に顔を出すことになる。
立花の簡略化
江戸時代になると草庵風の茶室と武家好みの書院造りの折衷様式、桂離宮などに代表される「数奇屋造り」という新しい生活空間があらわれる。
部屋の広さも八畳とか六畳の小間となり、床の間も簡素な造りで、壁や襖の装飾もほとんどない江戸の粋を象徴するかのようなすっきりとした空間が出現した。
江戸時代の高度成長期に「数寄屋造り」の建物が広がると豪華で大振りな立花ではその空間とは釣合わなくなった。
すると、茶花から発展してきたものと、立花の流し枝を取り入れ簡素にいけた二つの流れから起こったとされる「抛入花(なげいれはな)」が登場して立花に替わって「抛入花」ブームが庶民の中でおこる。
数寄屋造りの床の間には「茶花」では物足りず、「立花」ではおうぎょうすぎ、その中間の規模のすっきりした空間に合う性格のいけばなが求められたのであった。
そこで新興流派が爆発的に派生するのだが、当初、千家流、古田流、遠州流、石州流など、茶の湯の流派名が多いのもこのためである。
それまでのいけばな流派としては、立花を専門家業にしていた池坊の一流しかなかったのである。
「抛入る」とは枝葉を曲げていれるという意味で、立花のような「しん」のない花である。
花を自然の状態を保つように花を活かすことを主体においていた。
規範らしきものもなく、ある程度自由にいける花であった。
ちなみに当時は「いけばな」ではなく「いけはな」と清音で発音していた。
しかしブームの先行で理論の整理が追いつかない内に、床の間にいけるのに、花を投げ入れるとは何事かなどといった誤解も起こり、床の間にはそれなりの法式が必要だということになり、そこで、次に立花と抛入れの中間的な構成を取り入れた「生花」が出現するのである。
ここに時代に合わせるという過程で「生花」(せいか)がまた法式を持つ様式として生れることになる。
江戸時代のいけばな造形は、数奇屋作りに代表される簡素な床の間にふさわしい生花様式の完成を目指し、多くの流派が興り持論を展開してしのぎを競った。
その隆盛ぶりは浮世絵にも盛んに取り入れられ、女性のたしなみとなって発展してゆく。
これが江戸時代後半期を代表するいけばなとなった。
ここでも生花を家業とする流派が多くできるのだが、その理論は一様に専應口伝にある基本的な美意識の考えや、過去に著された既存の考え方を共通にしているものが多かった。
そこで差別化をはかるため、時代の古さや、関係ないと思われる偉人にそのルーツを求めたりする流派が多く出た。
立花の衰退から生花の隆盛で、立花を独占してきた池坊も無視できず、生花が成立して約百年後に生花(しょうか)として取り入れざるをえなくなる。
生花を「しょうか」としたのは立花の左右半分にして役枝を少なくした立花に比べて小さな花態であるとしたためだ。
事実、生花のその成立の過程と役枝の姿、配置から、立花の役枝を少なくして派生してできたとする説明のほうが信憑性が高いものと思われる。
続々と現れる多くの流派にあって理論家として一目置かれたのが、前期の「五大坊卜友(ぼくゆう)」と、生花にとって最終理論となった考え方を示した「未生斉一甫」である。
生花の造形理論
当時の各流派の花伝書には技術に関する記述は多いが、美の体系や造形論といった理論的な記述はそう多くない。
美学上の記述は「池坊専應口伝」に初見することができるが、天明五年(1785年)刊行の五大坊卜友の「生花草木出生伝」では陰陽五行の相を形に表すのに五つの役枝で規矩を決め、花形を半月にして、それを陰。半月が創りだす花形を陽と定め、そこに配された役枝を天地人三才を象形するという理論を発表した。
卜友は、この理論より後発の流派は皆天地人三才の規矩より分かれているのだから、いたずらに私意をもって新しい規矩を立てるよりも古人の正意をわきまえ、
諸流通用の規矩とするよう規格統一を提唱した。
流派が乱立し、天地人の三才格に各流が勝手な名称を付けるのはひいては「生花様式」の矮小化につながるということにおいて今日的問題なっている名称の不統一がいけばな界のグローバル化を阻んでいることを思うと先見の明があったといえるのだが、そういわしめるほど急激に流派が乱立していった現象として捉えることができる。
現にこのグローバル化の進んだ現代で、教育の場でもいけばなを説明するときに各流の構成する枝の名称がバラバラで生け花の発展の障害になっている事実は否めないのである。
江戸後期に生花理論を完成させた未生斎一甫は文化十三年(1816年) 「生花百錬」を著す。
生花もその成熟期に入り、おおくの生花の流派がおこった中で、花をいけるに当たって理屈は関係なく、ただ上手に生けられればいいとする風潮や、変わった形や、複雑化、単に形のための形を求めるといった新しいいけ方に重きが置かれていた時代にあって、花とは何か。どうして美しく咲いている花を切っていけるのかということを自然に問い、己の心に問いかけた。
その結果「未生自然の花矩(はながね)」という体系にたどりつく。
「天地創造に当たって、混沌としたカオスが生命の根源として存在する。ということから始まって、宇宙観、生命観をいけばなの中で追求していくという当時の自然科学に基づく理論を展開する。
東洋思想から西洋の天文学にまで言及し、そこから人間と自然との本質論を展開している。
その未生自然の花矩とは「天円地方説」という宇宙観から成り立っている。
天を円形、地を正方形で表し、円に正方形を内接してできた図形に天、人、地の三才(三つの働き)を配し、天と地の間に森羅万象が存在するとして「天地間の形するものにこの三角形より出ざるものなし。」とした。
古くはガリレオの人体図にもみられる構図だが、明治時代に登場する盛花の造形理論にも引き続き同じ図形が用いられていることはたいへん興味深い。
この天・地・人の長さの比は、西洋の「黄金比」(1:0.618)とほぼ同じで「白銀比(はくぎんひ)」(1:0,708) )とも呼ばれ、美しい構成比をもつ。
紀元前五世紀の西洋のギリシャと、東洋の日本の江戸時代に共通の美の構成比を持った。
さらに一甫は、格外に枝や蔓(つる)が伸びるのを臨機応変に働かせることを認め、「格に入って格を出よ」と説いた。
これによって既成の規躯に拘束されることなく、自己否定によってさらに美の追求を可能とする自由な芸術論を持つことになったのである。
当時この新鮮でアカデミックな考えは庶民に広く受け入れられ盛行することになる。
未生流二代目をついだ未生斎広甫は大覚寺の華務職となり、精力的に多くの未生流の著作を世に出し、この先、未生三百といわれるほど多くの未生流系の諸流が興ることになる。
ちなみに、遠州流は約八十流派以上に、古流は百以上に分派している。
このようにして江戸時代の後半にいけばなは大きく花開くのであった。
(いけばなの美学-2 終 )
- コメント ○ご自由にお書き下さい。 (認証コードをお忘れなく!)
a:8540 t:1 y:1